エネルギー講演会
「地球温暖化をめぐる国際情勢と日本の課題」
(10-7)
●したたかに対応する中国の情勢
そういう中で非常にしたたかに対応しているのが中国です。中国はもともとロシアとの間で経済協力関係を強化してきました。
北京五輪の真っただ中でロシアとの協力協定を結び、ロシアからの化石燃料の調達を増やすことを合意したわけですが、その中でロシアからの石油・天然ガスが西側のマーケットに行き場を失うことになると、中国はロシアの石油・天然ガスを追加で調達するということを現にやっています。パイプラインを通じてロシアの石油・天然ガスをしかも安く調達することによって、中国はエネルギー安全保障の点において西側の先進国よりも有利な立場にあるということになります。しかも、ロシアからの石油・天然ガスはホルムズ海峡を通る必要がないので、エネルギー安全保障という点でも中国は有利な立場にあります。実に悪賢い対応をしているといえます。
●先進国と途上国との認識の違い
2022年6月にドイツでG7のエルマウ・サミットが開催されて、ウクライナ戦争の最中にどういったメッセージが出るかが注目されましたが、読んでみると、やはり欧米の影響が強いのか、グラスゴー気候協定1.5℃といった温暖化に関するメッセージが非常に前面に出ています。他方、エネルギー安全保障の結果、ヨーロッパのガスは問題だということです。従って化石燃料への新規投資は2022年末で終了するという原則を書きつつ、ロシアのエネルギー依存の脱却のためにもLNGの供給は大事だと書かれています。だからヨーロッパがロシア依存を脱却するためにLNG投資をすることについてはまあまあ正当化されるでしょうと、ある意味、ヨーロッパ保護主義のような共同声明を合意したわけです。
ところが、G20の見解は違います。11月の終わりにG20サミットが開かれますが、その前哨戦として9月に、G20議長国であるインドネシアのバリ島でエネルギー大臣会合や環境大臣会合が開かれ、私も見てきましたが、G7とG20の相場感は全然違うわけです。
構成メンバーを見ても、われわれにとって親しみのあるG7諸国というのはG20の中の半分以下であり、中国、ロシア、インド、インドネシアなど、G7ではないG20諸国はロシアの経済制裁には全然乗っていないということですし、温暖化についても、1.5℃とかグラスゴー気候協定などをG20の大臣会合の中で入れ込もうとすると、中国やインド、サウジアラビアなどが反対するということです。
つまりG7というのは、1970年代にこそ世界の経済を引っ張る中心にいたわけですが、いまやG7の世界のエネルギー消費量あるいはCO2排出量に占めるシェアは25〜30%程度となっています。残り80%を占めるG20が圧倒的に影響力があるわけですね。そのG20の議論というのは、われわれが新聞などで読むG7の議論とはずいぶん違います。
エネルギー危機の中で一番苦しんでいるのは途上国です。途上国は一人あたりの所得が低く、化石燃料への依存度が高い。化石燃料の額が上がっている。エネルギーロスというのは所得が低いほど逆進性があるので、所得の低い人や国ほど、エネルギー価格の暴騰に対しては脆弱なわけです。
G7が行っている議論は、世界の脱炭素化を進めるために化石燃料への投資はやめなければならない、途上国はこれからのエネルギー需要の増大は再生可能エネルギーや省エネでまかなっていくべきである、という議論をしていて、それは途上国から見ると極めてダブルスタンダードであると映ります。
つまり、ヨーロッパは自分たちのロシア依存を下げるためにLNG投資を進めることを正当化しながら、途上国が化石燃料の不足に苦しんでいて、その不足を克服するために新規投資が必要だと言うと、二国間の輸出信用や国際金融機関などを通して、途上国の化石燃料プロジェクトが実現することに対してさまざまな形で邪魔をしていると映るわけです。
そういうときに途上国に影響力が増す可能性があるのが中国です。中国は基本的に価値観に従って外交をする国ではないので、おそらく途上国で化石燃料の需要があるのであれば、「われこそは途上国の立場に立って化石燃料をシェアします」と言うでしょうし、ウクライナ戦争によって世界が分断されていく中で中国が途上国に対する影響力を増していくということは、日本を含めた自由世界にとって、決して等閑視をできないだろうと思うわけです。
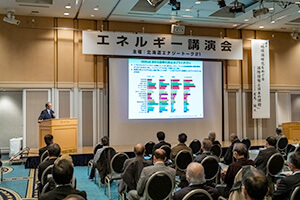
≪講演会の様子≫
