|
奈良林 日本のエネルギー政策に関する基本方針を示す最新の「エネルギー基本計画」が2010年6月18日に閣議決定されました。その内容をご紹介します。
エネルギー政策基本法は2002年に議員立法で制定されました。そのときに関わった国会議員の方々を私も存じ上げていて、ごく一部ですが、エネルギーに関して超党派で勉強会をやっていた先生方もいらっしゃいます。日本の法律は一度制定されるとよほどのことがない限り改定されませんが、この法律のすばらしいところは、「エネルギー基本計画」については3年ごとに検討を加え、必要があれば適宜改定するというルールを設けていることです。ですから、世の中の状況に応じて改善されていくという特長を持っています。
今回の改定のポイントですが、1番目はわが国の資源エネルギーの確保と安定供給、エネルギーの安全保障をどう考えるか。
 2番目として、地球温暖化対策の強化、包括的なエネルギー政策を謳っています。これを前提として、1990年比で2020年までに温室効果ガス25%削減という目標を基本としています。
2番目として、地球温暖化対策の強化、包括的なエネルギー政策を謳っています。これを前提として、1990年比で2020年までに温室効果ガス25%削減という目標を基本としています。
3番目がエネルギー・環境分野に関して経済成長の牽引役としての役割を持たせるようになりました。2009年12月に閣議決定された「新成長戦略」では、基本方針として日本は環境エネルギー大国になると謳われています。つまり、現在は世界各国が成長を遂げている中で日本は元気を失っていますが、こうした状況から国を再び成長させるための牽引役としてエネルギー・環境分野を位置づけようというものです。原子力や省エネなどの技術を輸出したり、その分野で雇用創出を図ろうという趣旨です。
4番目がいちばん大事で、国民との相互理解と人材育成を挙げています。今日も大勢の方にお越しいただいていますが、このような機会を通じて国民との相互理解が大事だということです。人材育成については、大学あるいは小・中・高校できちんとした正しい知識を子どもたちに提供することだと思います。つまり、国民に積極的に情報を提供して、理解と信頼を確保しながら進めていくことが大事です。
特に大事なのはこの部分です。「新たなエネルギー需要構造や社会システムの変換は、エネルギーを利用する国民や事業者の意識・行動様式の変革なしには進まない」。皆さんや我々も含めて、みんなが生活のしかたを変えないと、こういうことが達成できないという意味です。
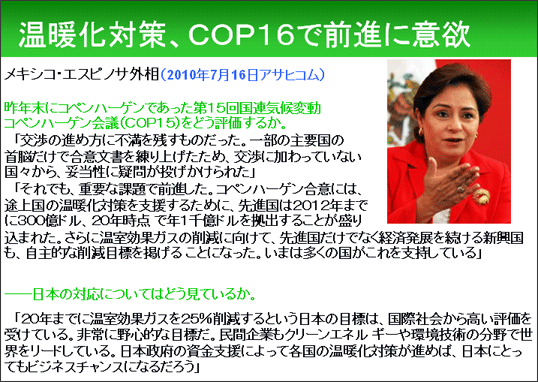
温暖化対策として、12月にメキシコで開催されるCOP16があります。昨年末にコペンハーゲンで行われましたが、世界中から集まって議論しても最終的に決まらず、合意が得られませんでした。つまり、進め方がまずくて一部の主要国だけで作ってしまい、新興国から異議が出たため、結局まとまらなかった。次のメキシコでは同じ轍を踏むことなく、合意を取りつけて前に進めるかどうかがCOP16での課題だと思います。
|