|
奥村 では、泊発電所について具体的な話をしていこうと思います。これが現在の状況です。新規制基準適合性審査は2013年7月に始まっていますから、ほぼ2年半続いています。
火山については、洞爺火砕流の影響なし、火山を監視すれば対処できるということです。津波に関しては10m以上の津波を想定することで了承されています。破砕帯は存在しません。活断層については、北海道電力が調査をしてもまったく見つからなかった断層が、敷地直下にあるのではないかという主張を一部の研究者がしていましたが、それもないと考えていいだろうと今年5月29日に結論されました。さらに、震源を特定しない地震動についても10月23日に了承され、いま基準地震動を決める最後の手続きに入っています。
参考:シンポジウム後の12月25日、基準地震動は概ね了承されました。
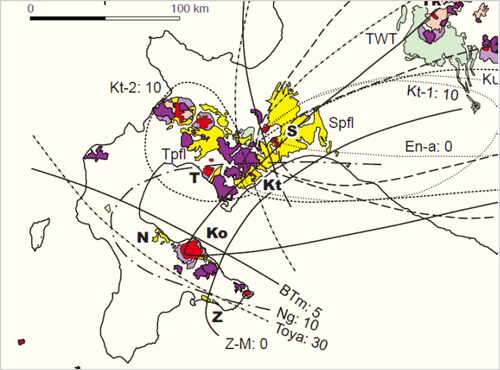
火山について、洞爺湖から出てきた洞爺火砕流が黄色で示した部分ですが、黒松内から岩内付近までこのような範囲で分布しています。この点線の範囲が泊発電所に達しているかどうかが議論の焦点でしたが、達していないという北海道電力の見解は了承され、仮に達していたとしても大丈夫だという話をしています。
というのは、九州電力の川内原子力発電所は、3万年前と9万5千年前に実際に火砕流が来ています。しかし、今後稼働している間に来る可能性はないということです。万が一そういう危険があってもモニタリングをしていればわかるはずだという結論が出ています。
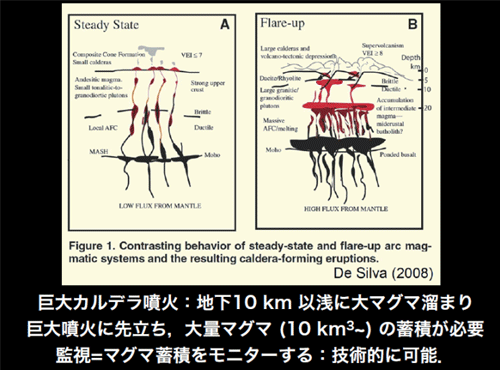
これについて簡単に説明しますが、いま洞爺湖は眠っています。その周りで有珠山などが小さな噴火をしています。もしもこういうところで洞爺湖のような巨大噴火が起きるとしたら、地下に10立方kmぐらいの液体を溜めておかなくてはなりません。固い岩盤の中に溶けたマグマが10立方kmも溜まったら、検出できないわけがない。さらに、それを溜めるのにも時間がかかります。少しずつマグマが供給されるたびに地面は膨らんでいくので、巨大噴火と小噴火は全然違うものなのです。
例えば、2014年の御嶽噴火は、立方メートルで図る程度の噴出物しかありませんでした。しかし、洞爺火砕流は20立方km。日本最大の阿蘇カルデラは400立方kmです。そうすると噴出物にして200立方km。もとのマグマはもっと密度が高いので10〜30立方kmぐらいになります。それを溜めるのにどれぐらい時間がかかるかというと、洞爺規模の噴火だと、1立方kmのマグマを溜めるのに1000年かかります。20立方kmのマグマを溜めるのに2000年かかる。そう考えたら、これは絶対検出できないわけがないのです。
いまお話ししたことが、IAEAそして規制委員会がガイドラインとしている基準です。いま火山学者たちは「我々の科学的な知識は不十分だからいつ起きてもおかしくない、起きないとは言えない」と反論しているわけですが、どうでしょう。いままでの火山の噴火の歴史と現在のマグマ蓄積の探査技術で、数十年、数百年は活動しないだろうという判断はおそらく妥当であろうと思います。規制委員会では、この問題について火山学会から申し入れられた検討を進めていますが、これまでの判断を覆すような意見はいまのところ出ていません。
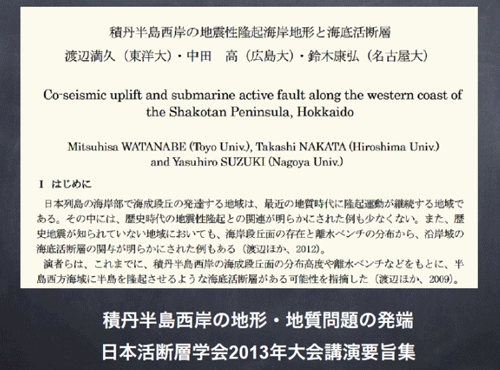
5月に解決した原子力発電所直下・近傍活断層の問題については、いくら海底を調べてもはっきりとした断層はないということです。しかし、積丹半島の海岸を見ると、昔に海で溜まった地層や海岸段丘と呼ばれる地形の高さが変わっているところがあり、その高さを変えたのは地震だという主張がずっと行われています。
ここに挙げた著者たちがさまざまな学会で、この主張を繰り返しています。ちなみに、この鈴木康弘さんは、私が先ほど鋭く批判をした新規制基準の活断層に関する部分を作った人です。この人たちが審査ガイドの草案を作っています。地震波を使った探査で、地下に断層が見えない場合でも、ほかに断層で説明できるものがあれば「断層が見えなくてもあるものと考えなさい」という主張ですが、こんなおかしな話はありません。活断層は地表に達しているものだから、あれば見えるものなのです。
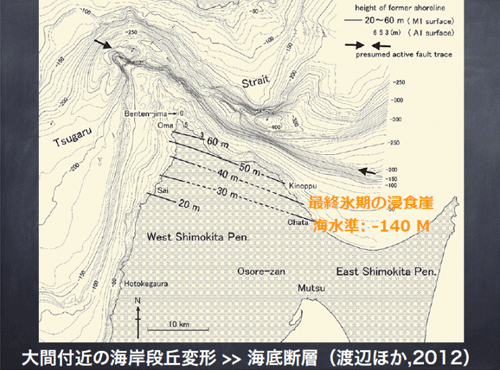
この著者たちは大間でも同じことをやっていています。これは12万年前の大間の海岸線で、波打ち際のひな壇状地形が残っています。その上に、11万5千年前に洞爺カルデラができたときに噴き出した火山灰が乗っています。実際に大間に行くと、平らな土地が11万5千年前にできたとわかりますが、それが南に向いて急に高度を落としています。渡辺さんたちは「この海底の崖は断層であり、ここで大きな地震が起きる」と主張したわけですが、電源開発は大間に発電所を作っています。彼らにとっては死活問題なので、詳細に海を調査しても「断層は一切ない」と言っています。
大間原子力発電所の設置許可申請は2010年以前に行われて設置許可が出ました。そのときに「この段丘の高度変化は地震によるものではない。渡辺さんは間違っている」という判断を原子力保安院も安全委員会も下しました。「断層はないから、この海岸段丘の傾きは他の原因でできた」という判断をしたわけです。渡辺さんたちはそれが気に入らないから、新しい審査ガイドの文言でも、ことさらに活断層を重視する内容になっていて、「これは大間のことを言っているな」と一目でわかるわけです。
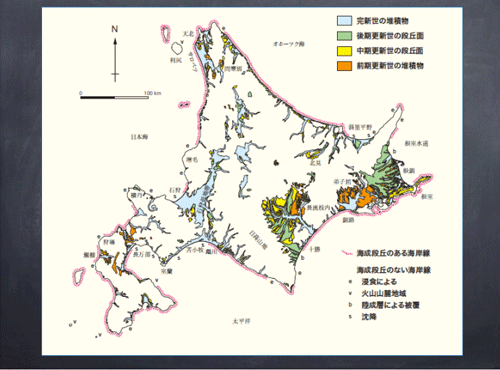
北海道の海岸は、ピンクの点々がある部分のすべてに海岸段丘があります。高さはさまざまで、奥尻に行くと120mぐらい、黄色が60mぐらい、黄緑が20mぐらいで、いたるところで高さが変わっています。知床や日高沖にはたぶん断層がありますが、その他の地域は断層のないところがほとんどです。ですから、高さが変化したら断層だというのは間違っています。断層で高度が変わることはありますが、高度が変わったら断層ということはありません。
そのように、最終的に審査ガイドでは泊発電所に「活断層なし」と結論が出ましたが、そのために非常に貴重な2年間が費やされたと思います。そういう意味でも、審査ガイド、規制基準は見直す必要があると思います。
次に、震源を特定しない地震動についても、非常に厳しい審査ガイドがつけられています。それは「活断層は出ないが、非常に強い揺れがあったら、それは泊でもどこでも起こるものとして考えなさい」ということ。どんな極端な揺れかというと、2008年岩手・宮城内陸地震では一関西(いちのせきにし)という観測点で4000ガル。1980ガルが16カ所ありました。例えばこのテーブルを9.8m毎秒ぐらいの加速度でギュッと押し上げてやると、テーブルの上のものは全部飛び上がります。その4倍のものが発生したと考えなさい、ということが審査ガイドに書かれたわけです。
結論から言うと、これらは観測点の性状、あるいはその局地的な特殊な地盤で大きな揺れが出たのであるといえます。今回の泊の審査でも、「この極端な揺れは泊発電所の岩盤の上で起きるような性質のものではないから、それは考える必要はない」という結論が出されています。ただし、そのために半年ぐらいの時間が費やされています。こうした極端で異常な現象はどこでも起こることはないというのが地震学の常識ですが、なかなか審査には反映されません。
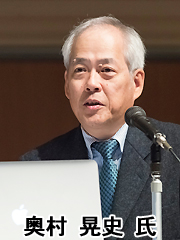 これからはいよいよ基準地震動で、原子炉や施設を設計するための地震動が策定されるわけですが、いまのところ北海道電力に対してあまり厳しい意見は出ていません。断層の連動や、地震を起こす揺れがどれぐらいの高さで起きるのかといった部分の見直しによって、いろいろと変化が出てくるかもしれませんが。 これからはいよいよ基準地震動で、原子炉や施設を設計するための地震動が策定されるわけですが、いまのところ北海道電力に対してあまり厳しい意見は出ていません。断層の連動や、地震を起こす揺れがどれぐらいの高さで起きるのかといった部分の見直しによって、いろいろと変化が出てくるかもしれませんが。
これは伊方発電所の例ですが、四国電力は当初54kmの断層を考えればいいと。一方、政府の地震調査研究推進本部では、この付近で起こる地震は110kmと言っていましたが、最終的に伊方発電所の新基準適合審査では480km、150ガルまで考えています。
「過大にしておけば安全」というような話が続いていますが、震災後のやや特殊な心理状態で法規が作られたわけですから、審査基準、審査ガイドともに、もう3年経ったから少し冷静に見直してもいいのではないかと思います。
さらに、規制委員会は一人の委員と事務局だけですべての案件の審査をしていて、2年半で300回の会合が行われています。個別の議事が非常に短く、数多くの専門家を集めることもなく、法で定められた原子炉安全審査会、核燃料安全審査会ともに審査機能を奪われています。さらに二次審査体制や審査結果チェック体制もない。そういうところで不確実・不確定の問題をどう合理的に解決するかということを、我々は真剣に考えていかなければいけないと思います。
|