|
小崎 次に、放射性廃棄物の処分の課題についてお話しします。福島第一原発事故後、「放射性廃棄物の処分方法もまともに決まっていないのに、どんどん廃棄物を出すような発電をするのはけしからん」といわれています。「処分が決まっていない」というのは、本当にそうなのでしょうか。
 低レベル放射性廃棄物は浅いところに埋めます。高レベル放射性廃棄物については、使用済み燃料を処理してガラス状に固めますが、そのガラス固化体については地下の安定な岩盤、つまり300mより深いところに埋めるということになっています。実はこのように、処分方法は決まっております。 低レベル放射性廃棄物は浅いところに埋めます。高レベル放射性廃棄物については、使用済み燃料を処理してガラス状に固めますが、そのガラス固化体については地下の安定な岩盤、つまり300mより深いところに埋めるということになっています。実はこのように、処分方法は決まっております。
また「処分が全然できていない」という方がいますが、低レベル放射性廃棄物については、青森県六ヶ所村に処分場があり、すでにドラム缶に詰めたものを処分しています。ただし高レベル放射性廃棄物については、日本の場合はまだ処分場が決まっていません。
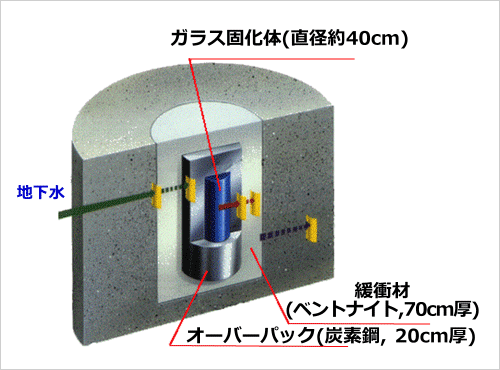
では、高レベル放射性廃棄物をどのように処分するかについてです。「穴を掘って入れるだけならまずいだろう」と思っていらっしゃる方は多いと思いますが、実際にはこのような「ガラス固化体」という形で処分することになっています。中心にはガラス状に固めた放射性廃棄物があり、その周りを炭素鋼の分厚い容器で囲みます。さらに外側には粘土を置きます。ちょうど荷物を送るときの緩衝材のようなもので、外側の岩盤の変形などを柔らかいもので緩和する働きがあります。さらに、放射性廃棄物を吸着するものなので、これを周りに置くと非常にうまく処分ができ、安全性が確保できるのではないかということで、こういった処分方法がいま考えられています。
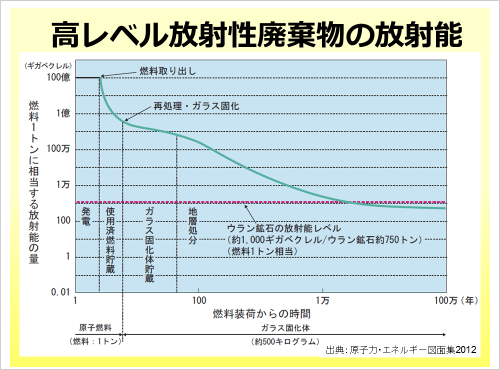
これは高レベル放射性廃棄物の放射能を表したグラフです。緑の線が高レベル放射性廃棄物の放射能で、赤い線はウラン鉱石の放射能です。原子力発電では、ウラン鉱石からウランを抽出し、濃縮して燃料として使っています。これを原子力発電所で核分裂させると、核分裂生成物のセシウムやヨウ素ができ、放射能が7桁程度まで増えます。
ラドン温泉やラジウム温泉のようにウラン鉱石をお湯に浸けるとちょうどいいですが、放射能が7桁に上がるとそんな悠長なことは言っていられません。ただ、放射性廃棄物には半減期というのがあって、時間とともに放射能がどんどん減っていきます。数万年も経つと、もともとの天然のウラン鉱石と同じぐらいの放射能になります。
ですから、高レベル放射性廃棄物を10万年ぐらい地下に埋めておけば、放射能は安全な領域になるというのが処分の考え方です。「ガラス固化体に使う容器は10万年も持つのか」と思われるかもしれませんが、10万年持たせようとはしていません。この容器は1000年ぐらい持てばいいでしょう。重要なのは、システムとして安全をどう確保するかということです。
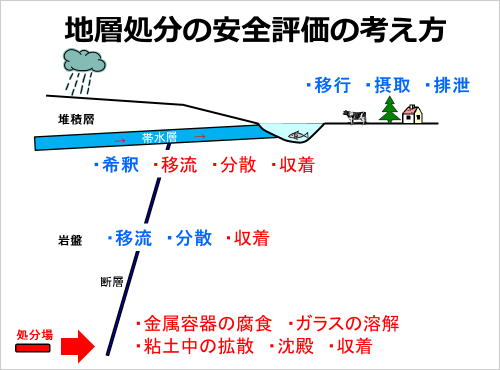
この図では左下に処分場があります。ここに処分すると1000年後に容器が腐食して穴が開き、ガラス状の放射性廃棄物が溶け始めます。もしも下流に断層があったとすると、断層は地表に向けたエレベーターのようなものですから、地下水が流れてくると、放射性物質もこのエレベーターに乗って上がってくるかもしれません。
ただし、上がってくるまでの間に薄まったり広がったりするでしょう。あるいは岩盤にくっついて動かなくなるものもあるでしょう。さらに地上に上がってくると、帯水層といって、地下水の流れに放射性物質が混じってきます。少量の放射性物質が大量の地下水と混ざれば希釈されるでしょう。さらに、人がこれを全部飲むわけではありません。こういうことを考えていくのが安全評価です。
このように具体的にさまざまなシナリオを作り、データを入れて計算して、安全基準に対してどうなのかを評価します。1000年後に金属容器が壊れ、1万年後に少し移行するが被ばく量はどうかなど、安全基準と照らしたうえでいいかどうなるかを計算し、安全基準と照らしたうえでいいかどうかを判断するのが安全評価のやり方です。ですから、1万年や10万年もの間、金属容器を持たせようとか、ガラス固化体がまったく溶けないということを前提にはしていません。あちこちに動きがあっても、その現象をすべて把握したうえで評価をしようというのがいまの進め方であり、これは世界各国でも同様です。
11月12日、フィンランド政府が高レベル放射性廃棄物の最終処分場建設に許可を出しました。どういう流れかというと、処分場の候補地を決め、地下に調査施設などを作って詳細に調べながら最終的に建設許可を求めるという道筋で、それに対してこのたびフィンランド政府から許可が出たわけです。
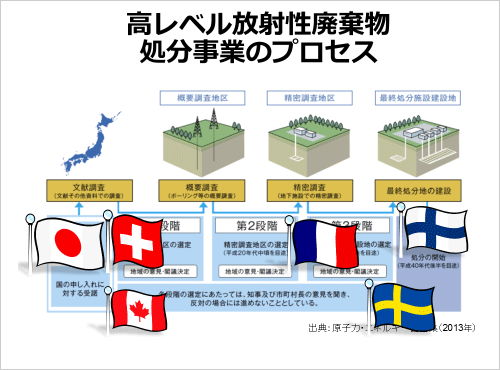
高レベル放射性廃棄物の処分事業については、フィンランドと同様、スウェーデンもいいところまで進んでいます。次がフランス。カナダとスイスは少し遅れて進んでいます。日本はまだまだの状況で、これをきちんとしていかなければならないというのが我々の課題です。
実はフィンランドに長く付き合っている研究者がいて、その彼に一度尋ねたことがあります。「なぜフィンランドでは処分事業がそんなに順調に進むのか」と。すると彼は「なぜ日本ではそんなにうまくいいかないのか」と言うのです。
フィンランドでは、30年ぐらい前から手順をしっかりと踏んで処分事業を進めてきています。最初に102カ所の候補地を決めて絞り込み、2000年には国が「原則決定」を行って、ぶれない政治を進めている。その結果、国の許可が出たということです。
日本とフィンランドで何が違うかというと、彼が言うには「フィンランドでは長期にわたって政治的な関与をしている。国家戦略を策定して国がしっかりやっていることと、信頼と責任が明確である」ということです。そこで「信頼と責任とは何か」と聞いたら、「国に対する信頼。原子力研究者に対する信頼。国も研究者も責任を持ち、国民もまた廃棄物を出すことに対する責任をしっかりと感じている。そこが違うと思う」と言われました。さらに、フィンランドでは市民との対話もしっかりやっているそうです。日本でもやっていると思いますが、なかなかうまく進まない状況があるようです。
|