|
竹内 最後の「環境性」についてお話しします。発電するときにCO2を出さない原子力発電を止めていることによって火力発電がこれだけ増えているので、震災前と比べて日本のCO2排出量は1億トンぐらい増えてしまいました。ちなみに、それまで日本が1年間に出すCO2は13億トンぐらいでした。
ちなみに国連の会議は皆さんのイメージと相当違うと思います。なぜあんなにまとまらないのか、不思議に思う方も多いようです。その理由はいくつかありますが、根本的には「自国の経済成長制約になるような炭素制約は負わない」ということが言えます。
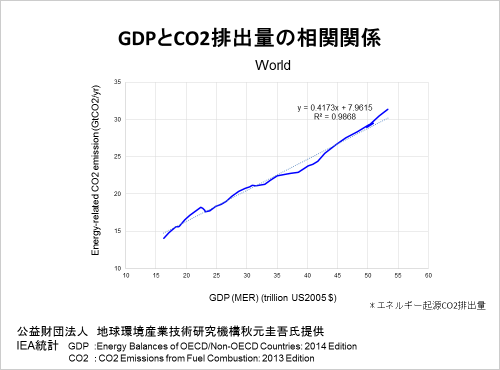
その意味は、グラフを見ていただくとよくわかると思います。横軸はGDPで、経済活動の活発さを表し、縦軸はCO2排出量。GDPが伸びると排出量も増えるわけです。よく「グリーン成長」といって、経済活動を活発にするけれどもCO2排出量は増やさないという考え方がありますが、歴史的にはそういった成長に成功した事例はほとんどない。ということは、国際交渉の場で「わが国の排出量をここまでに制限する」と交渉官が約束することは、「わが国の経済成長をここまでに制限する」ということを約束することにもなりかねないわけです。
そのため、国際交渉の場では「わが国は一生懸命やっている」、あるいは途上国であれば「わが国はいままで何も発展していなかった、温暖化は先進国のせいだ」と言って先進国に削減をさせようとします。そういう形で「あなたがやるべきだ」という押しつけや批判をするのが国際交渉で行われている議論の本質です。
日本では「わが国の目標が足りないと批判された」というのを嬉しそうに書く日本のメディアが多いですが、それは当たり前とも言えます。
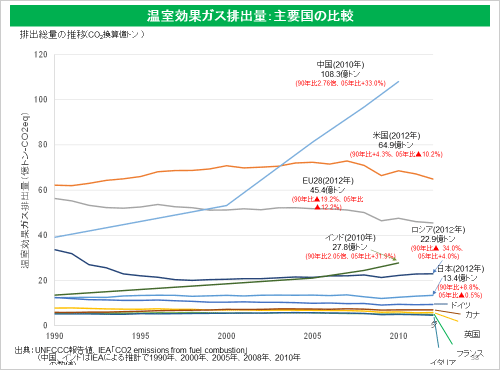
2015年11月30日〜12月11日、気候変動枠組条約第21回締約国会議(COP21)がパリで開催されます。温暖化対策でいま本当に必要なのは、このようにCO2排出量の伸びが著しい中国と、先進国で一番大きいアメリカに参加してもらうこと。主要排出国が全部参加する枠組みを作るために、COP21に向けて議論が進められています。
日本はCOP21に向け、「2013年を基準として2030年に26%削減する」という目標を掲げました。ちなみに、アメリカの目標は「2005年を基準として2025年に26〜28%、EUは「1990年を基準として2030年に40%」です。基準年も目標年もなぜこんなにバラバラなのかと疑問に思うことでしょう。これは、どの国も自分の数字が大きくなるように選んでいるわけです。
EUは、1990年という四半世紀前を基準にしています。なぜかというと、1990年ごろから東西ドイツの合併など東欧革命が始まりました。それまで効率の悪い機器を使っていた東ヨーロッパに西側の技術が流入しました。そこから経済成長はしたけれども、CO2排出量は減り始めたわけです。そこで、減る前を出発点にしておくと、現時点からの削減分は小さくてもすごくたくさん削減しているように見えるのです。
アメリカも同じです。2005年を基準年にしているのは、この年ぐらいからシェールガスの使用量が増えてきたから。それまで石炭を使っていましたが、国内にシェールガスという天然ガスが出たので、それを使い始めたらCO2排出量が減り始めました。減り始める前を基準年にすると大きく見えるからこうなったということです。このように自分たちの目標が最もきれいに見える“お化粧”をしていることがよくわかります。
|