|
小崎 最後に人材育成についてお話しします。先ほどお話しした高レベル放射性廃棄物の処分事業は100年プロジェクトです。スタートしてから、掘って、埋めて、最後に全部閉じるまでに100年かかるといわれています。中には、大学出て就職すると最後まで見届ける人がいるかもしれませんが、多くの場合はプロジェクトを最後まで見られないだろうと思います。そうすると、知識の継承をしながら人材を育てることが絶対必要です。廃炉も20〜30年かける場合が多いといわれますが、やはり人材を育てなくてはいけません。
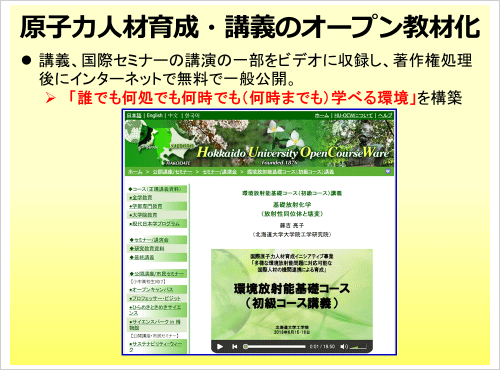
北海道大学では、工学部だけでなく他学部の先生方と協力しながら、原子力に関する講義をビデオに撮ってインターネットに無料で流すという試みを始めています。これは「オープン教材」といい、誰でもどこでもいつでも、先生や講師がリタイアしてもそれを学べる環境を作り、維持する試みです。
北大のホームページから辿っていけるこのようなホームページに動画があり、それでいつでも自由に無料で勉強できます。いま19講義が収録され、再生回数は5000回ぐらいになっていて、少しずつ認知度が上がっています。
 また、2015年度は「グローバルMOOC」という英語版の公開講座を行いました。日本では唯一、北大の私どものプログラムにオファーがあり、7〜8月に開講して世界133カ国の約3600人が受講しました。国内外に原子力の知識をできるだけ広めると同時に、安全に対する考え方や技術に対する考え方をしっかり学んでもらえる環境を維持していくことが重要だと考えています。 また、2015年度は「グローバルMOOC」という英語版の公開講座を行いました。日本では唯一、北大の私どものプログラムにオファーがあり、7〜8月に開講して世界133カ国の約3600人が受講しました。国内外に原子力の知識をできるだけ広めると同時に、安全に対する考え方や技術に対する考え方をしっかり学んでもらえる環境を維持していくことが重要だと考えています。
また、原子力人材、特に放射性廃棄物の処分に関わる人材を育てるためには、講義だけでなく実際の研究施設も必要です。道内には幌延町に深地層科学の研究施設がありますので、こうした施設を活用させていただきながら、北海道の地の利を生かした人材育成を進めていきたいと考えています。
|