|
竹内 電気代の値上がりついて、原子力発電所の停止に伴う火力発電の利用による燃料費増大ということだけで理由をお話していました。もう一つ、電気代が上がっていく理由があります。
皆さんのお宅の検針票に2012年7月から加わっている「再エネ発電賦課金」という一行です。このスライドにある検針票には803円と書いてあります。これは再生可能エネルギーに対する応援のお金です。「800円ぐらいだったらいいかな」と皆さんおっしゃるかなと思います。私も800円ぐらいだったらいいかと思います。が、これは800円のままではなく、これから増えていきます。
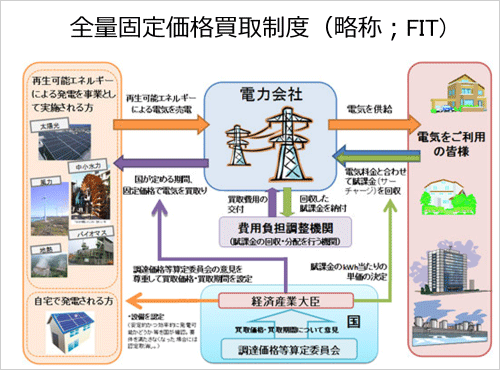
民主党政権時代に、再生可能エネルギーをとにかく急速に増やそうと普及政策を大きく見直し「全量固定価格買取制度」を入れました。これは、再生可能エネルギー事業者さんが太陽光や風力で発電した電気を、全量固定の価格で長期間、電力会社が買い取るよう法律で義務づける制度です。北海道では、北海道電力さんが買い取ることを義務づけられています。
北海道電力さんは、再生可能エネルギー事業者さんが発電した電気を買い取り、自分が発電した電気を合わせてお客さんに売ります。ここで問題になるのが価格の差です。
北海道電力さんが、昔からある水力発電や火力発電などいろいろな電源をうまく混ぜ合わせて電気を作ると1kWhで17〜18円、ここではわかりやすく20円ぐらいで発電ができるとします。ただ、再生可能エネルギーはまだコストが高いわけですね。
仮に、1kWhの電気を再生可能エネルギー事業者さんが40円かかって作るとしましょう。ということは、20円で電気を作ってお客さんに売る北電さんに対して「40円のものを仕入れてきて売りなさい」ということを義務づける法律です。では、その差額の20円はどうなるでしょう。お客さんが「ただの電気じゃなくて再生可能エネルギーの電気がいい」と、食に例えるなら「普通の大根じゃなくて、オーガニックの大根がいい」と望んだのと同じだから、この20円の差額はお客さんが電気代に乗せて払いなさい、ということです。電力会社に払うように見えますが、電力会社は素通りして、再生可能エネルギーの事業をする人にお金が行くわけです。
北電さんが再生可能エネルギー事業者さんから買い取るお金は、年に1回、政府が委員会を開いて決めます。つまり「いま風力発電を始めるとこのぐらいお金がかかる。その投資を回収して少し儲けを出すためには、1kWhの電気をいくらで買い取ってもらうことにしよう」ということを決めるわけです。
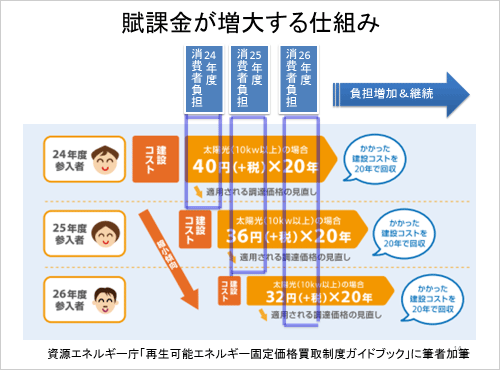
それを前提に、賦課金が増大する仕組みについてお話しします。
この制度がスタートした平成24年に事業を始めたAさんがいるとします。Aさんの発電する電気は「1kWhあたり40円で、20年間買い取ってあげなさい」と北電さんに義務付けます。翌年、Bさんが同じくメガソーラーを始めたとします。ただし、初年度の平成24年から1年経ち、太陽光発電パネルが普及したおかげで値段も下がっているので、Bさんが作った電気については「36円で20年間買い取ってあげよう」となります。翌年、Cさんがメガソーラーを始めたときにはもっと値段が下がったので「32円で20年間買い取ってあげよう」というように、買い取るお金は徐々に下がっていきます。当初はこのことが強調されたので、「技術が普及すれば消費者の負担が下がっていく」というイメージを持っている人が多いと思いますが、まったく逆です。
1年目、私たち消費者が負担するお金というのは、Aさんの電気を買い取るお金をみんなで割ればよかった。2年目は、AさんとBさんが発電した電気を買い取るお金をみんなで割ります。3年目は、Aさん、Bさん、Cさんの分を負担します。こうやって事業をやる人が増えていったら、消費者の負担はだんだん増えていくわけです。
例えば、制度の5年目ぐらいにパッと検針票を見たら、803円だと思っていた1カ月の賦課金が、いつの間にか1,500〜2,000円になっているかもしれません。私も、数百円の単位だったら再エネの応援に使いたいと思いますが、1,500円や2,000円になると厳しいと思います。
では、そういう声が世論で高まって、「再生可能エネルギーの普及政策を見直そう」と時の政権が決めて、この制度が廃止となったとします。廃止された瞬間に、皆さんの検針票から再エネ発電の賦課金の一行が消えると思いますか? 消えません。なぜなら、20年間買い取ると約束しているからです。そのように、この制度の怖いところは、負担が徐々に増え、さらに継続するということです。
この制度が入ってからの2年間、つまり2014年夏までの間に、再生可能エネルギー事業者から提出された申請書類の束を政府が計算をしたところ、「全部の設備が稼働を開始したら、国民の負担が年間2.7兆円になる可能性がある」との試算が出ました。この数字は1年間なので、20年間の累積だと最低約53兆円、最大約85兆円に膨らむという試算すら出ています。再エネのサポートにこれだけのお金を使うということを、日本国民は約束したことになってしまっていますが、いま政府は委員会を組織し、この制度の見直しを焦っています。しかし、なかなか進捗していないという状況です。
 この法律ができたときを振り返ると、福島第一原発事故が世間の空気に大きく影響していました。本来はエネルギー政策として、国民負担と再生可能エネルギーの着実な拡大について議論すべきだったと思います。再生可能エネルギーは電気を作る手段でしかないと思いますが、当時は原発という悪をやっつけるヒーローのように思われ、感情に流れた議論をしてしまったことが影響しているのではないかと思います。 この法律ができたときを振り返ると、福島第一原発事故が世間の空気に大きく影響していました。本来はエネルギー政策として、国民負担と再生可能エネルギーの着実な拡大について議論すべきだったと思います。再生可能エネルギーは電気を作る手段でしかないと思いますが、当時は原発という悪をやっつけるヒーローのように思われ、感情に流れた議論をしてしまったことが影響しているのではないかと思います。
それが法律にも如実に表れています。「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達に関する特別措置法」の中で、私は、法律の制度設計が失敗していることの象徴的な条文が「附則第7条」だと考えています。
「再生可能エネルギーの集中的導入を図るため、この法律の施行から3年間は、特に再生可能エネルギー事業者の利潤に配慮するように」と書いてあります。「利潤に配慮する」という内容が法律に入っているのはあまりにもおかしいと思います。利潤が適正であればいいですが、原資は何かというと国民の皆さんの負担です。案の定、この利潤が大きくなりすぎたために、国民の負担が大きくなっているということを申し上げておきたいと思います。
再生可能エネルギーのもう一つの問題点は、導入の直接的コストが高いだけでなく、不安定性を吸収するために送電線を整備するお金も必要になるということ。ある前提条件のもとでの試算では約1兆1,700億円かかるといわれています。なお、20〜30年後に廃棄されるときのコストについては、試算すら出ていないのでお話ができません。
いまお話ししたように、電気料金は、原発の稼働停止による燃料費の増大と、再生可能エネルギーの導入に関わるコストという点で、日本は二つの上昇要因を抱えています。それを何とか抑制したいということなのか、2016年4月に、家庭部門も含めて全面小売自由化が行われます。皆さん、家庭の電気は北電さんからでなくても買えるようになるということです。
自由化したら電気代が下がると思っている方が多いのですが、諸外国の歴史を見ると、自由化によって電気代が引き下げられたという明確な実証ができている国はありません。最初の数年は下がった国もありますが、上昇に転じてしまった国が多いのです。
自由化のことだけで1時間半ぐらいお話をしたいところですが、時間がないので報告書を紹介させていただきます。『諸外国における電力自由化等による電気料金への影響調査』という日本語での報告書があります。インターネットでタイトルを検索していただき、お目通しいただけるといいかと思います。
|