|
神津 ありがとうございました。今日は「再生可能エネルギーの可能性と課題」というテーマでお話しをいただきました。
最後ですが、私は「変わったこと」と「変わっていないこと」、「変えられること」と「変えられないこと」を分類して考える必要があるのではないかと思っています。
「変わったこと」といえば、世界の価値観をはじめさまざまにありますが、「変わっていないこと」を見ると、例えば地球環境問題の重要性はちっとも変わっていません。昨年は、北極海の氷床が非常に早く溶けたということがあり、環境問題は突然改善されるわけではないのです。
また、日本の人口はピークアウトしていますが、世界の人口は増え続けています。いずれ90〜100億人になるだろうといわれる中で、ますますエネルギーの確保は難しくなり、食糧も水資源も奪い合いの状況になるのではないか。いえ、もう始まっているかもしれません。
我々日本人は割とのんびりしているので、遺伝子組み換えは嫌だとか、無農薬がいいと簡単に言ってしまいますが、研究家の先生のなかには、「農薬や化学肥料、遺伝子組み換えという技術を進めていかなければ、食糧不足に陥る」という危機感を持っている方たちもいらっしゃいます。
地球の適正人口は30億人ぐらいだという話を聞いたことがありますが、現実的に人口が増え、90〜100億人になったときのことを考えれば、長期的に食糧やエネルギー、水などを確保するためには、それらを下支えする科学技術が進歩していかなければならないと思います。
日本も「変わったこと」と「変わらないこと」があります。例えば、日本は地震などの自然災害が多い国だということは変わりなく、これからもいろいろなことが起きるだろうといわれています。その中で私たちは暮らしていかなければならないわけで、そこに必要とされる技術をきちんと確立しなければなりません。
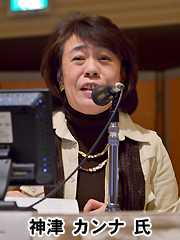 また、資源も突然増えたわけではありません。メタンハイドレートの開発により、日本は自前の資源を手にするかもしれないという話もありますが、それが現実のものになるまでどのぐらいかかるかはわからず、現在、無資源という事実も変わらないわけです。さらに、日本は金融国でもなければ、農業王国とも言い切れず、製造加工業の国であるということも変わらない。先ほどから出ている連立方程式の話のように、「エネルギー構造だけを変えたとしても、簡単に変わらない部分もあるのだ」という意識をきちんと持つ必要があるのではないかと思います。 また、資源も突然増えたわけではありません。メタンハイドレートの開発により、日本は自前の資源を手にするかもしれないという話もありますが、それが現実のものになるまでどのぐらいかかるかはわからず、現在、無資源という事実も変わらないわけです。さらに、日本は金融国でもなければ、農業王国とも言い切れず、製造加工業の国であるということも変わらない。先ほどから出ている連立方程式の話のように、「エネルギー構造だけを変えたとしても、簡単に変わらない部分もあるのだ」という意識をきちんと持つ必要があるのではないかと思います。
最近、ある新聞社の医療分野の方と話をしていて、私はとてもびっくりしました。今、エネルギー分野では、化石燃料を輸入するために年間3〜4兆円を海外に払っていると大問題になっていますが、同じように、日本で医薬品や医療器具に関して海外に流出するお金は、やはり年間3兆円ぐらいあるそうです。
つまり、どんなに国内での医薬品や医療機器の技術開発が進んでも、それらをきちんと日本のものとして存続させる努力をしなければ、その技術を海外のメーカーに取られてしまったり、外国のパテントになってしまったりという事態に陥るのです。それゆえに我々が払っている薬代や検査代のうち、3兆円ぐらいは海外に流出しているというのです。
太陽光パネルにしろ、日本が良いものを作っても、今や大半が中国メーカーで、家電やオーディオ分野でも日本のメーカーは凋落していく。日本が誇る技術力を、ただそれだけで満足するのではなく、自分たちの技術や国力をどのように守り続けていけるかということも、今の時代に大変試されているのではないかと思います。
長い時間、真剣にお聴きくださいまして本当にありがとうございました。私も昨夜札幌に来て、ホテルの暖かい部屋でテレビをつけたら、北海道電力の「節電のお願い」が出て、慌てて空調の温度を下げました。北海道の友人が「節電していると部屋の中の暖め方が違うので、融雪温度が低くて雪かきがかえって大変になる」と言っていました。やはりエネルギーというのは、生活を支える土台なんだと改めて痛感しております。
それでは、マイクを司会の方にお返しします。本日はどうもありがとうございました。

|