|
内山 では、またスライドで説明をさせていただきます。私も30年以上にわたって新エネルギーの研究をやってきただけに、やはりいろいろな形で普及させたいと思っています。そこで、今後の方向性を整理してみました。
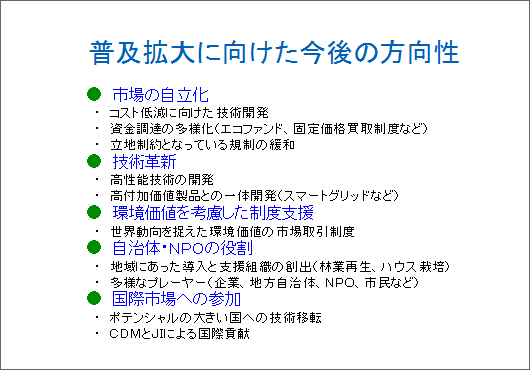
市場をいかに自立化できるか。それには、技術立国である日本は、コスト低減に向けた技術開発をさらに努力していく必要があるだろうと思います。しかし、資金をどう調達するかというのが非常に大きいものですから、その多様化を図ることが必要です。今回はエコファンドや買取価格制度ができましたが、しばらくはそういう資金援助制度を併用して普及していく必要があります。
また、どこまで国民に理解してもらうかも大事です。企業の負担がかなり大きいので、それを電気代にどんどん加算されると生活者も大きな負担になり、それだけ産業界も製造原価として上乗せせざるを得なくなる。そういうところを見極めながら、資金調達の多様化の必要があると思います。
また、立地制約となっている規制緩和についてですが、太陽光や風力などの新エネを導入すると、省庁の縦割り規制があまりにも強い。これを改善しないとダメですね。できるだけ省庁が協力し合って普及環境を整える必要があると思います。
 それから技術革新についてはまだまだ進歩が期待できるので、高性能技術の開発をしてもらう必要があるだろうと思います。もう一つは、高付加価値製品との一体開発として、電気自動車あるいは家庭のさまざまな電力メーターを含め、複合的な形で普及していく流れがあります。その一つがスマートグリッドで、そうした新しい産業として成長させていく必要があると思います。 それから技術革新についてはまだまだ進歩が期待できるので、高性能技術の開発をしてもらう必要があるだろうと思います。もう一つは、高付加価値製品との一体開発として、電気自動車あるいは家庭のさまざまな電力メーターを含め、複合的な形で普及していく流れがあります。その一つがスマートグリッドで、そうした新しい産業として成長させていく必要があると思います。
また、太陽光や風力などの再生可能エネルギーは環境価値が高いわけですが、これが今は外部コストとして扱われています。それを内部化し、価値を経済的に評価するというしくみづくりも必要だと思います。実際、導入にあたっては、自治体やNPOの役割、これが分散型ローカルエネルギーには欠かせないので、そうした方たちの協力を積極的に求めていく必要があると思います。
さらに、日本はこういう技術を作り上げて、世界市場に打って出なければならないと思います。再生可能エネルギーのポテンシャルというのは、日本よりも世界のほうが圧倒的に上です。いろいろな地域性を考えると、そういうところで日本の技術が成長していける環境づくりが必要かと思います。
|