|
内山
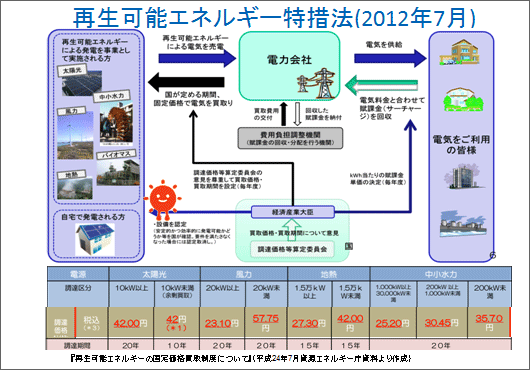
「もっと加速するためには思い切った政策が必要だということで、昨年7月に「再生可能エネルギー特措法」が施行されました。これによって再生可能エネルギーを電気料金の2倍以上、あるいはそれに近い値段で買い取り、機運を高めていこうというものです。こういう法律ができて非常に期待しているところです。
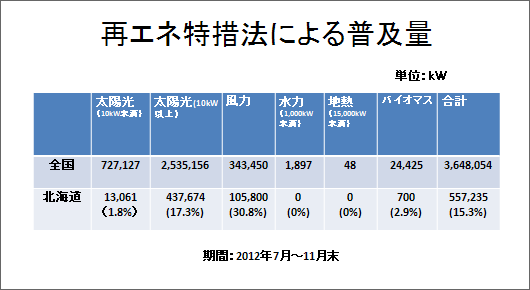
この再エネ特措法はまだ1年も経っていないので、状況を見ていく必要がありますが、7月以降、全国で約364万8千kWの再生可能エネルギーが導入されています。うち大半は太陽光発電で、特にメガソーラーが253万5千kWとかなりのシェアを占めています。
北海道を見ると、この間に日本全体の再生可能エネルギーの15.3%に相当する55万7千kWが導入されていて、導入量が一番多いのが風力。これが日本全体の31%近くを占めています。太陽光は17.3%という状況です。
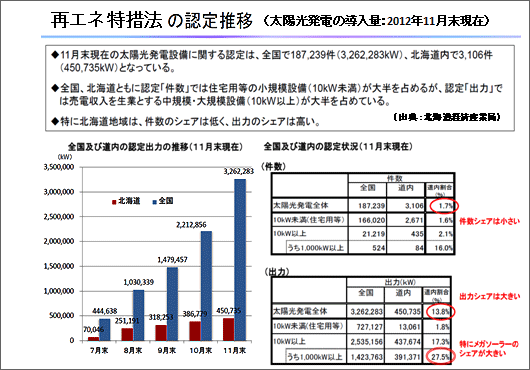
これは北海道経済産業局さんの資料を使わせてもらっています。特措法による太陽光発電の普及量は、3,262,283kwです。北海道では件数で1.7%、発電量で13.8%ということ。つまり北海道では、メガソーラーの普及の割に、家庭用の普及が極めて少ないということを意味しています。
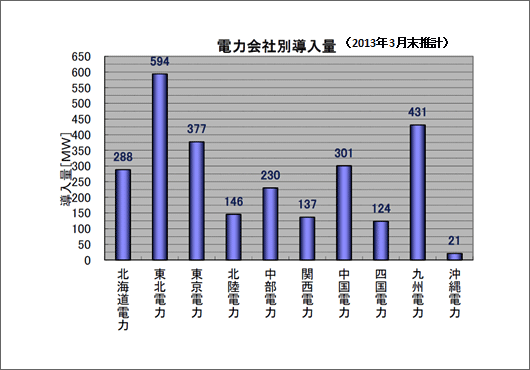
風力の場合、これは現在までの各電力会社での導入量を比較したものですが、一番多いのは東北電力です。次に九州電力、中国電力、北海道電力という順です。私から見ると、北海道はポテンシャルが高いはずですが、他の電力管内に比べると導入量が低いといえます。これは系統の接続問題、あるいは需要でしょうね。そうしたマッチング問題というのが北海道特有の課題として残されていると判断できます。
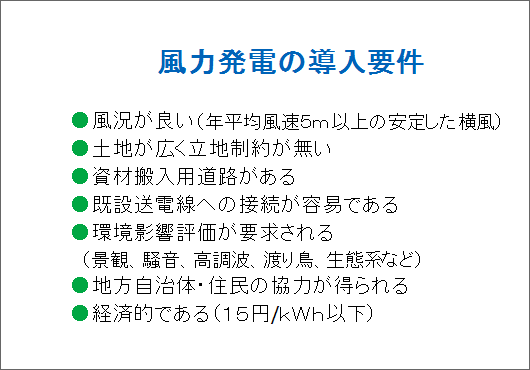
風力発電の導入要件ですが、まず風況が良くならなければいけません。最低でも平均風速5m以上は必要だということ。次に、土地が広く立地制約がないということ。それから、資材搬入用道路があること。既設送電線への接続が容易であること。さらに環境影響評価が要求されているので、それに適合されないといけません。導入に際しては、地方自治体や住民の協力が得られることが必要であること。さらに経済的であること。そういう要件が必要です。
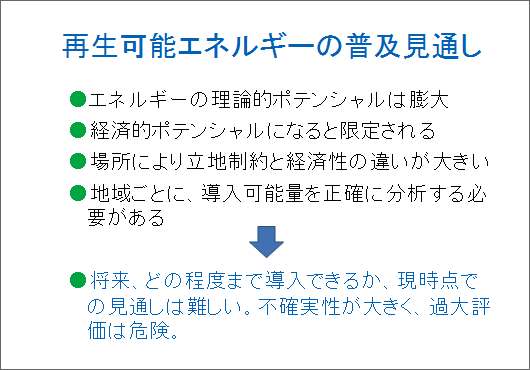
再生可能エネルギーの普及見通しについて、理論的なポテンシャルは非常に大きいといえます。しかし、経済的ポテンシャルとなると、どの国や地域でも非常に限定されてしまうという課題があります。場所によって立地制約と経済性の格差が大きいというのも特徴で、そういう点から、地域ごとに導入可能量を正確に分析する必要があるということが課題です。
ヨーロッパでいろいろな事例がありますが、地域ごとに特徴があって導入されていて、それらがすべて日本に当てはまるということにはなりません。将来どの程度まで導入できるのか、正直言うと、現時点での見通しは難しいといえます。不確実性が大きいために、あまり過大に評価するのはエネルギー政策上、非常に危険ではないかと考えます。以上です。
|