|
内山 実は私は、新エネ大賞の審査委員長を6年間務めていて、毎年表彰していますが、その中の事例をいくつかお持ちしました。
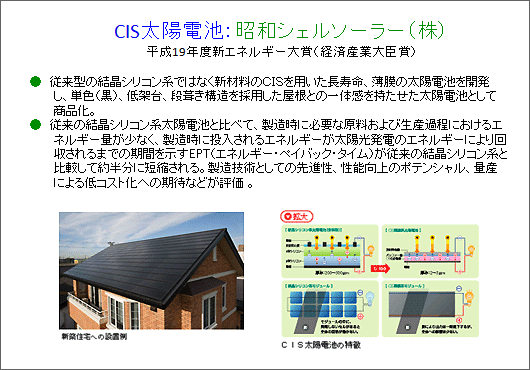
これはCISという新しい太陽電池ですが、実際に屋根に設置して効率の良いシステムを提案した技術です。日本はこういう良い技術を持っているので、さらに発展させていくことが大事だと思います。
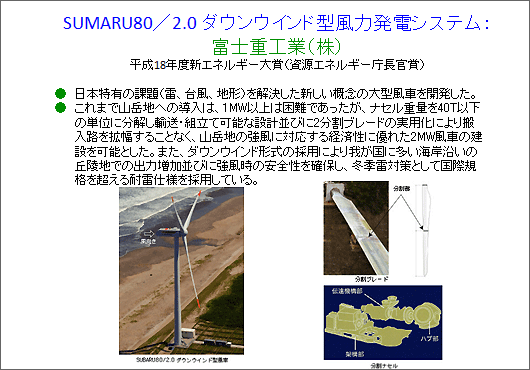
これは風車で、面白いのはダウンウインド型だという点です。風車の型には、アップウインド型とダウンウインド型があります。風車にはブレード(羽根)がありますが、出力が大きくなるとどんどん長くなってしまい、クレーンで運ぶのは大変なので、それを分割し、ブレードを折って運べるような風車です。現地でブレードを組み立てる技術で、これも画期的だということで表彰しました。
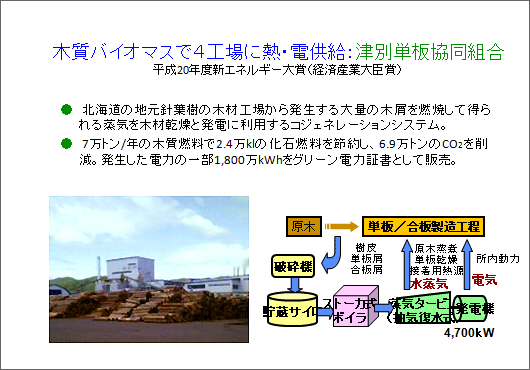
これは木質バイオマスで、経済産業大臣賞を受賞した津別町の事例です。木材を利用して工場内のあらゆるエネルギーを賄い、まさに地産地消型のエネルギーシステムとして非常に発展してきています。こういう事例も日本全国にたくさんあります。
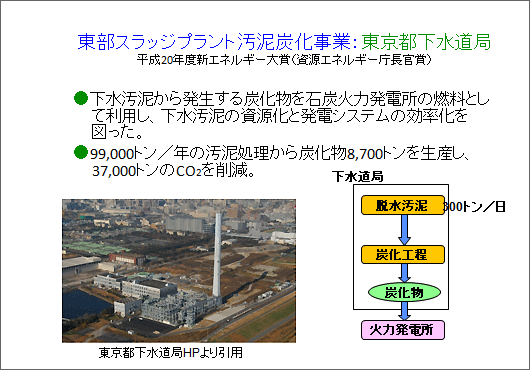
東部スラッジプラントは東京都の事例です。下水汚泥から出る炭化物を乾燥して石炭火力発電所の燃料にしました。これは立派な技術で、石炭火力の燃料に変えるという形で普及しています。
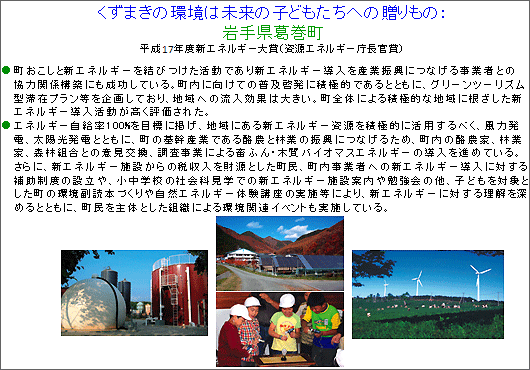
教育も大事です。これは岩手県葛巻町の学校ですが、総合的な新エネルギーを普及することでさまざまな教育活動に貢献しています。日本全国にそういう活動の芽はたくさんあり、さらに育てていくことが大事だと思います。
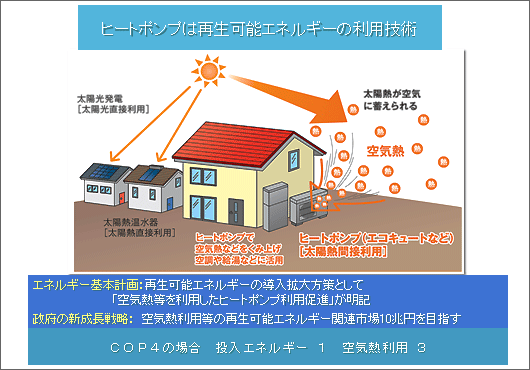
これはヒートポンプで、空気に蓄えられている熱を利用する新しい技術です。こうしたものも今後普及していけば、さらなる再生可能エネルギー利用の拡大になると考えられます。
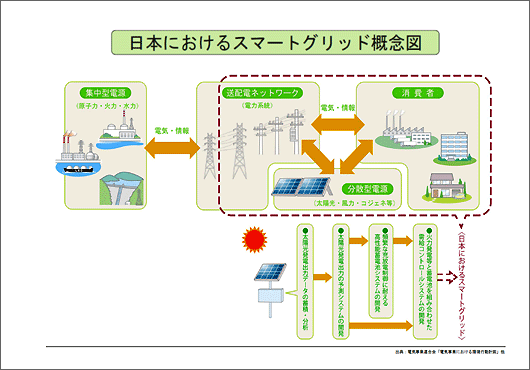
先ほどのスマートグリッドについては、現にいろいろな地域で検討されていて、北海道でスマートグリッドあるいはスマートシティに関する開発をお願いしたいと思っています。
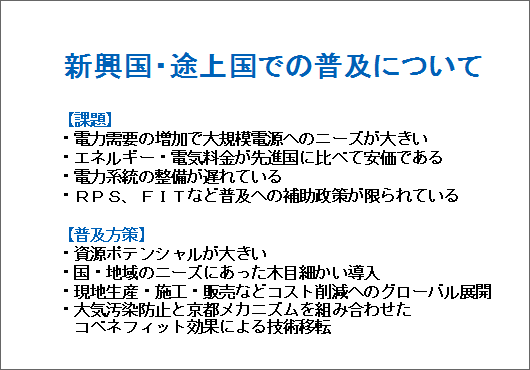
先ほど言いましたように、途上国や新興国に日本の技術をどうやって持っていくかということも課題です。こうした国々では、電力需要の伸びが大きく、大規模電源へのニーズが高いということ。また、エネルギー・電気料金が先進国に比べると安いので、高価な技術を持って行ってもなかなか売れない。どうやって安い技術を供給できるかということも必要です。
電力系統の整備が遅れているので、その対応も必要です。RPS、FITなど普及への補助政策が限られているので、現地のさまざまな問題をどう解決するかについて日本はもっと積極的に取り組むことで、こうしたインフラ産業を海外に展開していくこともできるかと思います。
そうしたことが可能であれば、資源ポテンシャルが大きい国々なので、日本の技術が広く海外に生かされるのではないか。それが地球規模の環境問題にも貢献できる将来につながることを期待しています。しかし、実際になるといろいろな課題があり、ぜひ皆さん方にも協力をお願いしたいと考えています。
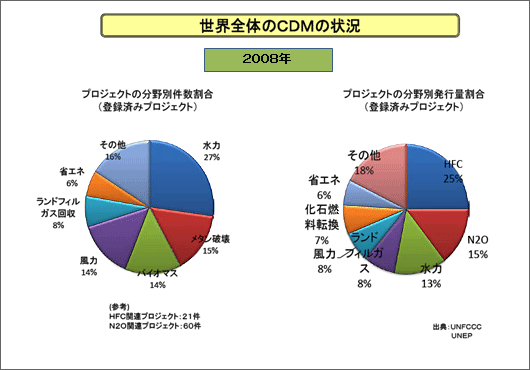
私はCDM(クリーン開発メカニズム)の研究を実施していますが、それを見ても登録済みのCDM案件には、水力、バイオマス、風力といった再生可能エネルギーの案件が非常に多くあります。これを利用して、日本は海外で展開していくことが期待できるのではないかと思っています。以上です。
|