|
山本

ここから温暖化の話です。この写真はアフリカです。アフリカでも大きい湖のチャド湖の水がない状態です。昔はナイジェリアやチャドなど4カ国にまたがる湖でしたが、いまその面積は20分の1以下になっています。この湖の水がなくなった原因の半分は人為的なことで、水の使いすぎです。もう半分は温暖化。温暖化で雨が降らなくなっています。
温暖化は、気候変動といわれるように、雨が降るところでは極端に降りますが、降らないところでは極端に降りません。アフリカはその影響をすでに受けています。アフリカの大半の国では、働いている人の8割ぐらいは農業に従事しています。温暖化の影響で雨が降らなくなると、農業ができなくなる。自給自足のアフリカにとっては死活問題です。こういう人たちが困るから温暖化対策を進めようというのが、国連の基本的な考え方です。
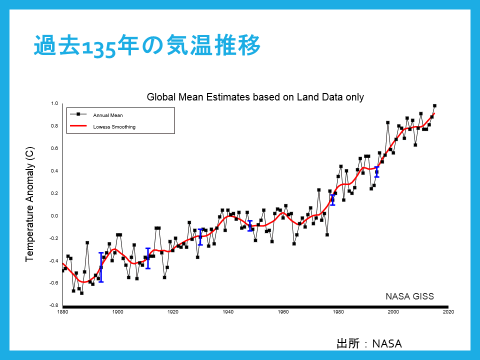
これはアメリカ政府の観測データで、135年の間に気温が1.2度ぐらい上がっています。なぜかと言うと、二酸化炭素が毎年増えていっているからです。光合成が活発な時期には二酸化炭素が減りますが、不活発な時期には増えます。

二酸化炭素の濃度を測っているのはこういう場所です。雪が積もっていますが、ハワイ島で標高4000m以上のマウナケアという山の上に天文台があり、反対側のマウナロアというところにアメリカの観測所があります。
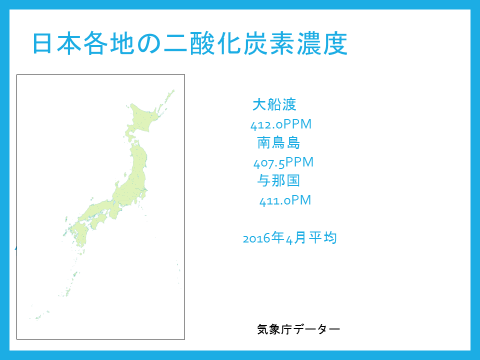
日本は大船渡、南鳥島、与那国の3カ所で測っています。ハワイ島とこの3カ所の共通点は、人為的活動がほとんどない地域だということ。要は自然の二酸化炭素濃度が測れる場所として、人があまり住んでいない場所が選ばれています。3カ所の二酸化炭素濃度はどれも400PPM以上。産業革命の時代は280PPMぐらいでしたから、それくらい二酸化炭素が上がっています。それが温暖化の原因です。
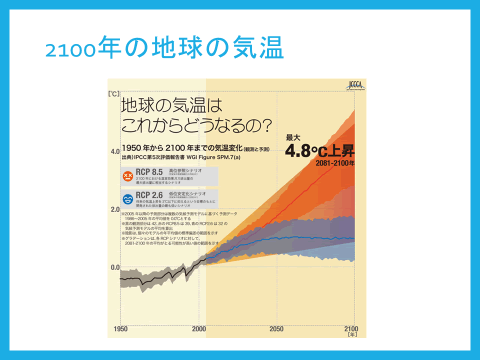
2100年の地球の気温は最大4.8度上がると予想されています。実は最小は0.3度です。予想にも幅があるので、2100年の地球の気温がどれくらい上がるかというのは全くわかりません。しかし、5度以上上がる可能性もある。もしも対策をしないと、さまざまなことが起こります。
環境省によると、例えばリンゴの栽培地は本州から北海道に移るなどの影響があるそうです。それはあまり問題ではないと思いますが、先ほどのようにアフリカの人たちのことを考えると対策をしたほうがいいので、日本は2030年までに温室効果ガスを26%削減するという目標値を定めています。同様に、アメリカとEUもそれぞれ目標値を定めています。
日本はこれを達成するために、電気の44%を原子力と再生可能エネルギーでまかなう、つまり二酸化炭素を出さない電源で電気を作ることを目標としています。
また、エネルギー効率を改善するという目標も立てていますが、たぶんできないと思います。なぜかと言うと、エネルギー効率が改善するためには、工場の設備が入れ替わらなければいけません。実はオイルショック以降、エネルギー効率は35%ぐらい改善しました。年率4〜5%で経済が成長すれば、設備投資をしてもエネルギー効率の改善になりますが、政府が想定している経済成長率は1.7%です。それで設備の入れ替えはできないでしょう。達成は非常に難しいといえます。
|