|
山本 日本で固定価格買取制度が始まったころ、ヨーロッパ各国は、再生可能エネルギーは電気代を引き上げるのでどうやってやめるかを考えていました。この後、ドイツは2014年に固定価格買取制度を原則廃止します。今年1月1日からは入札制度になり、安い値段でなければ電気は売れません。また、スペインは買い取り価格を遡及して下げました。スペインでは「法律を決める権限は政府にある。だからこれは有効」という判例が最高裁で出されました。イタリアは新たに税金を導入します。「太陽光発電を導入している人は新たに税金を払ってください」というものです。そういうことを各国が進めている最中に、日本は逆の政策を進めてしまい、電気代を上げて家庭にも産業にも影響を及ぼしているというのがいまの姿です。
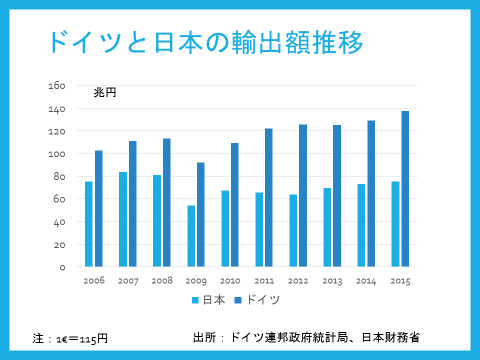
このグラフは、ドイツと日本の輸出額推移です。ドイツは伸びていますが、日本は全然伸びていません。なぜかというと、ドイツは電気代に仕組みがあります。輸出産業には、はるかに安い電気代が設定されています。日本の半分以下で、アメリカ並みの電気代です。
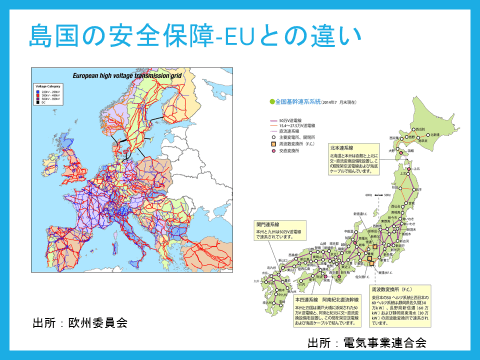
安全保障の話に移ります。ヨーロッパの送電線はつながっています。ヨーロッパとアジアとを分けるウラル山脈があり、この手前まで送電線がつながっています。シベリアまでは行っていません。ウクライナの大きな輸出産業は電気で、せっせとヨーロッパに輸出して稼いでいます。トルコ、中東、イスラエルを通ってエジプトまでつながっています。一方は、地中海を渡ってモロッコ、アルジェリアまでつながっています。イギリスはフランス、オランダにつながっていて、ノルウェーともつなげようとしています。電線も天然ガスも全部つながっています。
日本は、石油の8割以上、天然ガスの3割を中東から買っています。すごく怖いことです。ヨーロッパでは、一つの地域から3割以上買ってはいけないというルールがあります。現状でヨーロッパは、天然ガスや石油、石炭などの輸入量の3割をロシアに依存していますが、その状態を危ないと考えているわけですね。やはり相手が脅しのうまいプーチンさんなので、そういう人に3割も頼っているのは怖いから、何とかしようと必死です。
ところが、日本は3割どころではありません。1次エネルギーの約45%を中東から輸入しているという大変な状態です。でも、あまり危機感がありません。
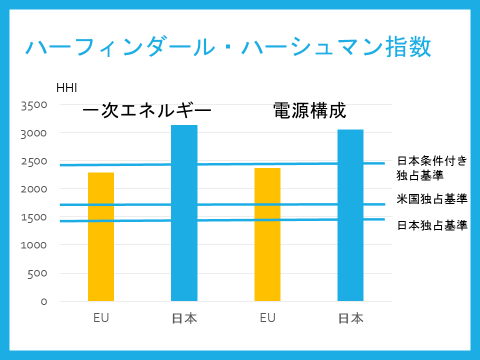
これは日本とEUに関してエネルギーの独占を表す指数です。指数が大きいほど独占が進んでいる、つまり分散が進んでいないということです。指数の小さいヨーロッパのほうが日本より分散が進んでいるということ。送電線もパイプラインもつながっていて、さらに分散が進んでいます。エネルギー安全保障の面では、ヨーロッパは日本よりいいポジションにいるということですね。
|