エネルギー講演会
コロナショックからエネルギーを考える
〜歴史から学ぶ危機脱出のヒント〜
(4-1)
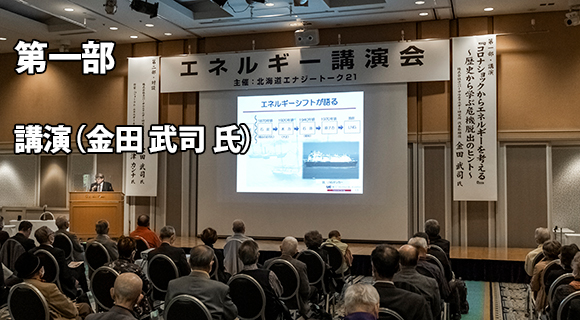
金田 武司 氏
株式会社ユニバーサルエネルギー研究所
代表取締役

工学博士。慶応義塾大学理工学部機械工学科卒業。東京工業大学大学院エネルギー科学専攻博士課程修了(工学博士)。(株)三菱総合研究所勤務を経て、2004年(株)ユニバーサルエネルギー研究所を設立。2018年8月に新著『東京大停電』を出版。現在は、東京工業大学大学院非常勤講師、NEDO技術委員など歴任。
●導入
今日は「コロナショックからエネルギーを考える」というお話です。

写真をご覧いただくと、海の上に船が浮かんでいます。漁船ではなくタンカーです。タンカーがこんなに集まっている光景。何だろうと思いますよね。これはLNGと石油のタンカーです。なぜこんなことになっているのか皆さんと一緒に謎解きしてみたいと思います。
第1話 コロナで見えてきたこと
●日本の国産マスクは2割?
 コロナショックの当初、話題になったのがマスクでした。私たちもマスクを手に入れるのに大変苦労をしました。日本以外の各国首脳はマスクに対して懐疑的でした。いまだに懐疑的な人はたくさんいます。例えば、フランスのマクロン大統領は当初、「マスクなんかいらない」と言っていました。しかし、あるとき突然、「間違いだった。マスクは大事なんだ」と方向転換をして、「国内と欧州でマスクの生産力を高めなければいけない」と言いました。マスクをしたくても、なかったらしょうがないですから。さらに「独立を取り戻す」という表現をしました。マスクの生産力を高めることと独立と、何の関係があるのかと思いますね。実は大いに関係があります。
コロナショックの当初、話題になったのがマスクでした。私たちもマスクを手に入れるのに大変苦労をしました。日本以外の各国首脳はマスクに対して懐疑的でした。いまだに懐疑的な人はたくさんいます。例えば、フランスのマクロン大統領は当初、「マスクなんかいらない」と言っていました。しかし、あるとき突然、「間違いだった。マスクは大事なんだ」と方向転換をして、「国内と欧州でマスクの生産力を高めなければいけない」と言いました。マスクをしたくても、なかったらしょうがないですから。さらに「独立を取り戻す」という表現をしました。マスクの生産力を高めることと独立と、何の関係があるのかと思いますね。実は大いに関係があります。
後でエネルギーの話をしますが、手に入ること、供給を受けられること、自給できることと、独立とは非常に関係があります。フランスは無防備で、海外に依存しすぎたということに気がついたんです。
さて、マスクは本当に重要なのでしょうか。日本の国産マスクは2割だそうです。マスクは不織布とひもでできていますね。これらは日本で作られていません。不織布もひもも日本で作られていないのに「国産マスクが2割」とはどういうことでしょうか。実は、不織布とひもを結びつけたのが日本であれば「国産」だということなんです。面白いですね。不織布とひもは中国製。2割が国産だというけれども、その材料は輸入です。要は日本国内では自給できないということ。したがって、皆さんもご経験の通り、マスクが手に入りませんでしたね。2割が国産でできるのだったらそんなことは起きませんから。
さて、私はいろいろ調べてみました。医療機器ではこのコロナ禍で人工呼吸器などが話題になりました。また、PCR検査では綿棒や防護服、マスクも必要です。それらは国内でどれくらい供給されているのでしょうか。
人工呼吸器は9割が輸入です。綿棒は日本でまったく作られていません。防護服やマスク用の不織布、ゴムひももすべて輸入です。びっくりですね。コロナに備えなければいけない中で、人の命を守るものが実は日本で作られていないということ。作っているとしたら、不織布とひもをつなぎ合わせることくらいだとだんだんわかってきました。つまり医療全体がかなり海外に依存しているということです。少しだけではなく、極端に海外頼みになっています。
●「国産」より「自給」できることが重要
私は「自給って何だろう」と考えてみました。そんなとき、コロナ禍でロシアが小麦を輸出禁止にしたという報道がありました。日本ではそんなに報道されていませんが、私はコロナ報道で一番びっくりしたのはこれです。食料の輸出を止めるとはどういうことを意味するのでしょうか。
日本では食料自給率30〜40%です。小麦もほとんど海外に依存しています。小麦がなかったら、日本の食生活は変わります。それを世界最大の輸出国であるロシアが輸出を止めたと聞けば「どうして?」と思いますね。
コロナ禍でヒト・モノ・カネの流れが停止して奪い合いが行われる可能性があるとすれば、自分の国を優先しますね。外国に輸出している場合ではなくなる。ロシアが輸出を禁止すると、他の国も追随しました。コロナでびっくりしたのは、こうした自国主義です。
さて、日本の食料自給率はカロリーベースで約37%。自給率は日本農林規格で定義されています。食料の場合の「自給率」とは、自分で供給できること。では「国産率」とは何かというと、不織布とひもを結びつけたのが日本であれば「国産率」は20%です。でも全部輸入です。矛盾していると思うかもしれませんが、国産と自給とは違うのです。
農林水産業で「自給」というのは、自分で全部作れること。すべて自分の手で賄えることです。例えば、牛が海外産の飼料を食べて成長し、その牛を流通させたら国産牛ですか、自給ではありません。食料自給率とはそのように考えられています。その牛が自給できる環境で育ったかどうか、大事なのはそっちなんじゃないでしょうか。
マスクの不織布とひもを結び付けたのが国内かどうかよりも、それ自体が日本で作れるかどうかということに、われわれは気がつかなければいけないんです。
わかりやすい例を言うと、昨日たまたま活力をつけようとウナギを食べました。ウナギの稚魚はヨーロッパでつくられています。どこで育てるかというと中国です。最後に国産にするためには、浜名湖でちょっと泳がせます。さて、これは自給でしょうか。これは自給ではありませんね。中国で養殖されていますから。でも、最後に浜名湖で泳いだら国産なんです。
このように、われわれがエネルギーでも食料でも自立する、自給できるということの意味を考えさせられる大事件がコロナだったというわけです。

≪講演会の様子≫
●マスク文化にみる他者への意識
ところで、皆さんはマスクを着用していらっしゃいます。日本人は真面目で、ちゃんとルールを守ります。日本人はなぜマスクをするのでしょうか。他人を守ってあげるためにマスクをするという文化があるからだと思います。自分さえ良ければいいということではなく、国民病とも言われた結核を抑制したという歴史にも通じるものがある。「罹っているかもしれないけれども、もしも罹っていない方がいたとしたら感染させてしまうかもしれない」と他者を思う意識が日本人にはあるのだと思います。
私が言いたいのは、セキュリティー、つまり身を守ることとは、他者との関係性により成り立つということです。後でエネルギーの話をしますが、他国との関係性によってエネルギーセキュリティーが成り立つんですね。
