エネルギー講演会
「激動の国際情勢と日本の課題
国家の安全保障とエネルギーについて考える」
(3-1)
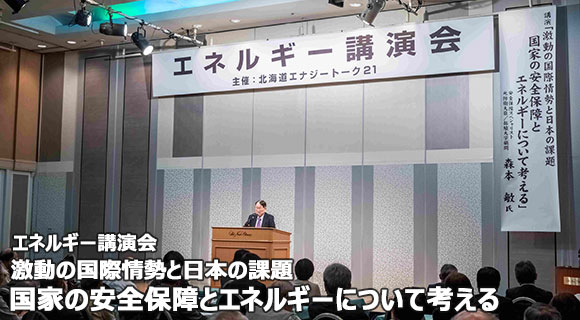
講師 森本 敏 氏
(安全保障スペシャリスト/元防衛大臣/拓殖大学顧問)

防衛大学校理工学部卒業後、防衛省入省。1977年に外務省出向後、1979年外務省入省。在米日本国大使館一等書記官、情報調査局安全保障政策室長など一貫して安全保障の実務を担当。退官後、慶應義塾大学、中央大学などで教鞭を執る。2016年3月から2021年3月まで拓殖大学総長を歴任し、同年4月から同大学顧問(現職)。2012年6月第11代防衛大臣就任(民間人初)。主な著書に『ウクライナ戦争と激変する国際秩序』(編著、並木書房、2022年11月)、『台湾有事のシナリオ』(共著、ミネルヴァ書房、2022年1月)ほか多数。
●冷戦以降の世界の動き
本日はまず、エネルギーと関連する問題として国際情勢からお話しします。
「冷戦」という言葉は、武力を使用することなく戦争と同じような状態にあることをいいます。第2次世界大戦後、超大国のアメリカとかつてのソ連が覇権を争って対立構造ができたときから、われわれはこれを「冷戦時代」と呼んでいました。
その中で、アメリカとその同盟国、アメリカと価値観を共有する国を「西側」、ソ連を中心とする社会を「東側」と言っていました。どちらにもくみしない国のことを「第三世界」「非同盟」と言っていました。その中心にいたのがインドと中国です。
ところが、冷戦期に地域国で戦争が起きるとき、例えばカンボジア戦争やベトナム戦争などでは、西側と東側がぶつかるのではなく、第三世界の国同士がぶつかるのです。
冷戦が終わってアメリカとソ連が対立状態でなくなってからは、そういうものが消えました。具体的に言うと、それは1989年、米ソ首脳によるマルタ会談が行われたときです。
1990年には、それまで東西に分かれていたドイツが一つになり、1991年にはソ連が崩壊しました。また、6カ国の東ヨーロッパの体制が崩壊したことに伴い、それらの国々はソ連に付いていたのでは社会主義経済のままで豊かになれないので、経済的には西側に入ろうという動きが出て西ヨーロッパの枠組みに融合していきました。

そのことにより世界はどのように分かれたかというと、アメリカは厳然として残り、ソ連はやや少なくなって残りました。旧ソ連の人口は2億9,000万人でしたが、うち約1億5,000万人がロシアになりました。残った約1億4,000万人はいまのウクライナ、ベラルーシ、バルト三国などが徐々にソ連から離れてしまいました。
そういう状態が、2000年から2010年ごろまで続きました。その間、世界はアメリカ一極主義でした。つまり、アメリカだけが大国であり、ソ連や中国はまだ大国ではありませんでした。
ところが2010年、中国はGDPで日本を追い抜いて世界第2位になってしまいました。世界のGDPは1位がアメリカ、2位が日本だったのに、中国が2位、日本は3位に落ちました。さらにドイツにも追い抜かれました。一人当たりGDPの順位はさらに低く、日本は先進7カ国で最下位、世界で34位(2023年、IMF統計)になり、韓国より低くなりました。
●世界秩序はどうなっているか
いまの世界は、アメリカという一国に対して、中国とロシアが向き合っている状態です。中国とロシアの関係は初めはぎくしゃくしていましたが、いまはエネルギーや原材料によってお互いに利益を享受しつつあります。
世界の秩序はどうなっているかというと、アメリカを中心とする自由主義社会。中国とロシアが連帯を組んでいる権威主義社会。そして、どちらにもくみしないグローバルサウス。この3つに分かれています。
スウェーデンの「V-Dem(多様な民主主義)研究所」という調査機関が2024年に出した報告によると、調査対象の179カ国・地域のうち、民主主義は91、権威主義は88。民主的な社会で暮らす人々は29%(約23億人)にとどまる一方で、権威主義は71%(約57億人)を占めました。つまり、世界の中で豊かでない国が非常に多いということであり、そうした国々にどうやって豊かになってもらうかが大きな課題で、その根幹にあるのがエネルギー問題といえます。
