|
澤 「健康」「経済」は果たして対立する概念なのかどうか。どちらが欠けてもうまくいかないという、むしろ補完的なものだと思います。ですから、対立させておいて議論すると解決策がなくなるのではないでしょうか。先ほど小沢さんがおっしゃったように、「リスクをどこまで引き受けるのか」ということについて議論せざるを得ないと思います。
実は、原子力は全体の約30%を占めるといわれていますが、震災以降はゼロです。大飯発電所が再稼働した以外、実質的に脱原発はなされているわけです。そうなると、この状況には耐えられそうな気がするかもしれませんが、ここで心配なのは、この冬が乗り切れるかどうかということと、電気料金が上がるかもしれないということです。
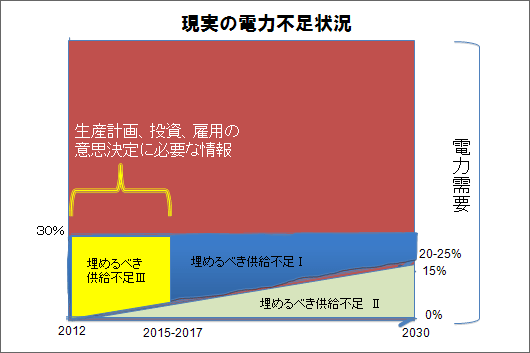
図をご覧ください。企業にとって、埋めるべき供給不足はこういう状況にあるので、この先3〜5年は黄色い部分の見通しが立ちません。泊発電所が動くかどうかわからないからです。つまり、この供給不足がどのくらいの量になるのか、どれくらいの値段になるのかということが、命を支える雇用にも関係してくるわけです。
もう一つは、原発を火力で代替したら、電気料金がいくら上がるかという問題。イメージ的には約2割です。中小企業にとっては毎月約75万円ずつ上がることになる。人件費でいうと3〜4人分ですね。もしも経営状況がカツカツの場合は、このコストアップ分をどうやって吸収するかが問題です。
電力会社なら電気料金に転嫁すればいいわけですが、中小企業はそれ以上転嫁できないので、自分たちで吸収せざるを得ない。給料を下げるか、社員を解雇するか、あるいは売上をアップするよう努力させるか、何らかの対応が迫られます。こうした経済への影響がすでに表れつつあるわけです。
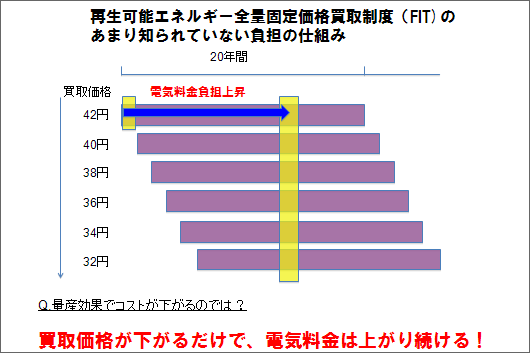
また、この図をご覧ください。再生可能エネルギー全量固定価格買取制度の負担のしくみについては、誤解されていることが多いようです。太陽光を買うときに「買取価格は42円」と言っています。あれは電力会社を経由して皆さんの電気料金にそのままアップされるわけです。「再生可能エネルギーを導入したらいい。どんどんコストが下がるから」と言う人は、はっきり言ってウソつきです(笑)。
そうではなくて、例えばこの42円に加えて翌年の買取価格40円をまた負担する。38円に下がってもさらに負担する。最初は42円で負担したこの黄色い額が、皆さんの今年の負担分ですが、数年後には、42円+40円+38円…となっていきます。ですから5〜6年経つと、5〜6倍負担が増えるということです。この点が非常に誤解されているわけです。
買取期間は20年続きますが、この制度を始めたら後戻りできないので相当の負担額になります。だからドイツは全量固定価格買取制度をやめたわけです。
日経BPのアンケート結果では、「原発をやめて電気料金が上がってもしかたない」という人の中でも「値上がりは2割以下に収めてほしい」という人が9割います。つまり「原発も嫌だ、しかし料金上げるのも嫌だ」という人がほとんどです。それが世論なんです。しかし、原発が止まって火力に代替された燃料費分として2割分上がり、さらに再生可能エネルギー固定価格買取制度で2割以上も上がってしまう。世論に流されるがままに、施策を考える側は解決策がない。
ではどうするかというと、政治家は先送りするわけです。「再稼働についての判断はもう少し後で」「電気料金の値上げよりは電力会社のリストラが先だ」という形でみんな先送りします。ユーザーである企業にとっては、先送りにより情報が確定せず、不確実性がすごく増してくるわけです。雇用するにも工場を作ろうにも確定した情報がなく、計画を立てることも難しい。要は、生活を支える経済をどれくらいリスクのあるものにしていくか。そういうこととのトレードオフになってしまうのが、エネルギー問題の難しさだと思います。 |