|
十市
私がエネルギーの研究を始めたのは1973年、第1次石油危機の直前に現在の研究所に入りました。それから現在まで40年ぐらいの間に、石油危機や今回のような原子力発電所の事故もあり、エネルギーについて先を見通すのはいかに難しいかということを大変実感をしています。特にいま日本の置かれている立場を考えるとそう感じます。
私がエネルギーの研究を始めた1973年は、日本はエネルギーの約8割を石油に依存していました。そこで、第4次中東戦争が起きたために石油が来なくなるというオイルショックがありました。トイレットペーパーなどがなくなって日本経済が大混乱に陥ったことを会場の皆さんもご記憶かと思います。それ以降、いかにエネルギーの安定供給を目指すかが課題となり、石油に代わるエネルギーとして、原子力のほか太陽光発電など新エネルギーの開発が40年前から進められてきました。
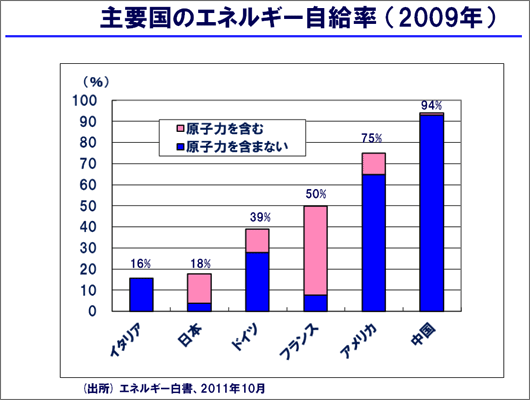
この図は主要国のエネルギー自給率の比較で、日本のエネルギー自給率は4〜5%。国内の地熱発電、太陽光発電、風力発電などを全部集めても4〜5%で、残り13〜14%は原子力発電です。「ウランは100%輸入だから国産ではない」という議論はありますが、原子力の場合は一度燃料を装荷すると3〜4年は安定的に使えますし、使った燃料を再利用すれば国産になることから「準国産エネルギー」という評価をしています。それを入れて日本は18%という自給率になります。
ドイツはこのたび脱原子力を宣言しました。国内に石炭がたくさんあり、自給率は39%。フランスは、電力の75%を原子力でつくっています。それを入れると自給率は50%です。アメリカは原子力を入れて75%。アメリカは国内でシェールガス(頁岩から採取される天然ガス)を生産し、天然ガスは完全に自給体制です。石油も新しい技術開発でどんどん生産が増えてきています。そういう意味では非常に高い自給率といえます。中国は90%を超える自給率です。
 こうして見ると、日本のエネルギー自給率は極めて脆弱です。食料自給率40%でさえ「もっと上げろ」といわれていますが、エネルギーについてはこれから相当努力をしても極めて低い自給率です。森本先生のお話のように国際情勢では難しい問題がある中で、日本にとってはエネルギーの安定供給が重要な課題です。しかも、いくら値段が高くてもいいわけではありませんから、経済面も考えて安定供給できることが大事です。いずれにしても日本の置かれている立場が脆弱だということは、過去40年間変わっていないと思います。
こうして見ると、日本のエネルギー自給率は極めて脆弱です。食料自給率40%でさえ「もっと上げろ」といわれていますが、エネルギーについてはこれから相当努力をしても極めて低い自給率です。森本先生のお話のように国際情勢では難しい問題がある中で、日本にとってはエネルギーの安定供給が重要な課題です。しかも、いくら値段が高くてもいいわけではありませんから、経済面も考えて安定供給できることが大事です。いずれにしても日本の置かれている立場が脆弱だということは、過去40年間変わっていないと思います。
特に、福島第一原発事故を受け、国内では原子力への依存度を下げようという動きが出てきています。どこまで減らすか、あるいはゼロにしろという議論もありますが、日本のエネルギー事情を踏まえたうえで国際情勢を見すえ、日本の経済社会や暮らしを維持するためにどうするべきかという冷静な議論をしなければならないと思います。
|