|
奈良林 これまでお話ししたほかに、原子力発電のすばらしさがもう一つあります。それは、燃料となる物質が運転中に炉心の中で生まれることです。
燃料のウランには、ウラン235とウラン238の2種類があります。ウラン235は天然ウランだと全体の0.3%くらいしかありません。それを3〜5%くらいまで濃縮して初めて軽水炉で使うことができます。残りのウラン238は、原子炉内で中性子を吸収してプルトニウム239に変わります。プルトニウムだけを取り出すと核兵器になってしまいますが、これを人類がエネルギーのために使うか、核兵器に使うか。
日本は平和利用ですから、当然これを燃料として使います。この赤い部分は核分裂生成物といい、「核のごみ」になります。核のごみは1トンの燃料を使うと30kgくらいできますが、それを取り出してガラスと混ぜ、ステンレス製の容器に入れ、溶接して保管し、冷えてから地中に埋める。これが核燃料サイクルの目指すところです。地中処分は人間がきちんとやればできることで、今後しっかりと進めなければなりません。これがいま課題になっていることです。
泊3号機でもプルサーマルが進められていて、燃料はMOX燃料といい、ウランとプルトニウムを混ぜた混合酸化物燃料のことです。これをウランと混ぜて炉内に均一に配置し、原子炉を運転します。そうすると、原子炉の中で作られた燃料を再び原子炉で使い、リサイクルができます。
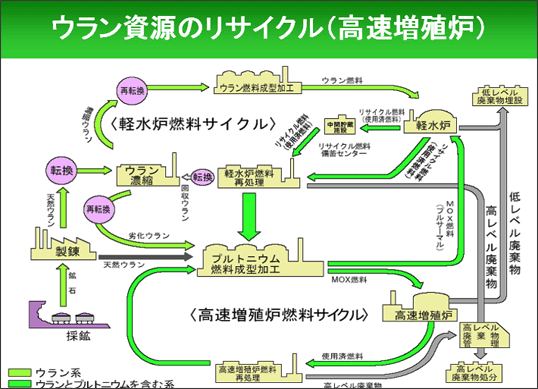
先ほど人類2000年分のエネルギーを得ることができると言ったのは、プルトニウムを効率的に作ることができる高速増殖炉を我々がしっかり作って、安全に使いこなしていくことによって初めて実現するものです。
日本では福井県の高速増殖炉「もんじゅ」が運転を再開しましたが、過去にはさや管が折れてナトリウムが漏れ、火災が起きました。それで14年間も止まってしまいました。反対運動があり、訴訟にもなりました。
ところがフランスは32年間に35回もナトリウムが漏れています。フランスはそれだけ漏れても、たゆまぬ技術努力を続けています。日本は1回漏れただけで止まってしまう国です。どちらが技術開発力がつくかは明白です。もちろん安全性は大事ですが、努力を続けられる国と止められてしまう国の違いは大きく、私はこのことが核燃料サイクルにとって非常に大事だと思っています。
核燃料サイクルは、軽水炉のサイクルと高速増殖炉のサイクルがありますが、高速増殖炉のサイクルが回り出すことで人類2000年分のエネルギーを得ることができるようになります。今後20〜30年の中で、ここまで到達することが大事だと思います。
|