エネルギー講演会
コロナショックからエネルギーを考える
〜歴史から学ぶ危機脱出のヒント〜
(3-3)
●日本の歴史の中にヒントがある
神津 これから先、日本に可能性があるとすれば、どのようなポイントでしょうか。
金田 私は歴史にもっと学ぶべきだと思います。これから先、新しいものが登場するのはそう簡単ではないですから、学ぶべきは、われわれがやってきたこと、つまり忘れている活力や努力やヒストリーだと思います。
日本は諸外国に例を見ないほどさまざまな経済危機を経験してきました。オイルショックだって、世界で一番被害を受けたのは日本です。日本が立ち直ることができたのは外国に頼ったからではなく、その時点では高かったかもしれないけれども、省エネタイプの家電など壊れず長く使えるもの。日本ブランドをつくり、災い転じて福とした。これが日本の原点だと思うんです。
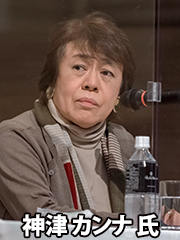 神津 私たちは歴史に学び、なぜ自給をしなければいけないと考えたのかなど、きちんと振り返らなければならないのでしょうね。
神津 私たちは歴史に学び、なぜ自給をしなければいけないと考えたのかなど、きちんと振り返らなければならないのでしょうね。
私は、北海道の送電線の保守点検を見せてもらったことがあるんです。雪の日に、山の中まで雪上車で行きました。途中で降りてスノーモービルに乗り換えて、さらに、滑り止めにアザラシの皮が逆さに貼ってあるストーという靴を履いて山奥へ行くんですよ。それで、送電線に雪や氷が着いていると、鉄塔に登り棒でカンカン叩いて落とすのです。すごく原始的ですよ。
こういう点検作業は、いつかドローンでやるようになるかもしれないし、融雪の機械ができるかもしれない。だけど、さっきの「つなぎの鍋釜」のように、ストーを履いて山の中まで行って、カンカンと棒で叩くような時代もあるわけで、北海道電力さんはそういう技術を育ててきたわけですよね。都会に住む私たちは、夢見心地のことを言ってしまったらいけないのではないかなと、そのとき思いました。
金田 電気事業ってそういうものです。われわれの見えないところでの努力がものすごくあって、見えているところは氷山の一角。そういう努力の上に電気のある生活が成り立っているんです。その努力は、長年培った経験によって組み立てられるんですね。原子力もそうですが、それをやめたらすべて捨ててしまうことになります。「本当にそれでいいんですか」というのが重要なポイントですね。
神津 いくら自動でできるといっても、エネルギーの輸送船が来なくなったら同じことですし、コロナで人の行き来ができなくなったら、送電線の氷をカンカンと叩く作業のような技術が必要ですよね。そういう技術が何のためにあるかを知っておく必要があると思います。
●危機脱出のために私たちができること
神津 それにしても、今生きている人は、東日本大震災も、ブラックアウトも、コロナも経験したのですからすごいことですね。教科書に載るような歴史的な出来事を体験したのですから。
金田 この経験をどうやって後世に伝えるかだと思いますね。
神津 「災い転じて福となす」じゃないですが、これを機に、私たちができることを考えなければいけないですね。先生はこのコロナ禍を通して、エネルギーに関して「これを考えてほしい」という宿題みたいなものはありますか。
 金田 宿題というならば、いま、この経済危機からどうやって抜け出せるか、日本の経済を復興するためにわれわれは何ができるのか、一人一人にぜひ考えていただきたいと思います。そのときに忘れてはならないのが、日本が経験してきた歴史です。過去にどうやって危機を脱出できたのかを振り返りながら、考えをまとめていただきたいと思います。
金田 宿題というならば、いま、この経済危機からどうやって抜け出せるか、日本の経済を復興するためにわれわれは何ができるのか、一人一人にぜひ考えていただきたいと思います。そのときに忘れてはならないのが、日本が経験してきた歴史です。過去にどうやって危機を脱出できたのかを振り返りながら、考えをまとめていただきたいと思います。
神津 もしかすると私たちは目先のことばかりで、考えなくなっているかもしれませんね。自給ができない日本ですが、いろいろなものが八方ふさがりの中で唯一の助けは、歴史に学ぶということですね。
金田 そうです。選択肢を自ら捨てることはないと思います。私たちは石炭で世界最高水準の技術を持っています。原子力も世界最先端の技術です。天然ガスも、一つ一つやってきたことを自ら捨てる必要があるのだろうか、取っておいたっていいじゃないかと思います。「こっちがダメなときにあっちにしよう」ということもある。選択肢を捨ててしまうことのリスクについても、また考えなければならないですね。
神津 自分で考えるというのは大事ですね。腸の専門家から聞いた話ですが、腸は第2の免疫器官だといいますね。腸の中の菌は約1割が悪玉菌で、約2割が善玉菌、あとの7割は日和見菌だそうです。つまり、体の中にある免疫はほとんどが日和見だということ。それを良い方向に持っていくためにコントロールできるのは自分しかいないのだそうです。ですから、自分で考えるということがすごく重要なんだと今日は思いました。金田先生、ありがとうございました。

≪対談の様子≫
