|
山本 電力システム改革は、競争環境を作り出し、選択肢を増やして電気代を下げようというのが目的でした。ヨーロッパではそれを進めている国もありますが、どこもうまく行っていません。なぜかというと、競争環境を作り出しても電気代が下がる保証がないからです。
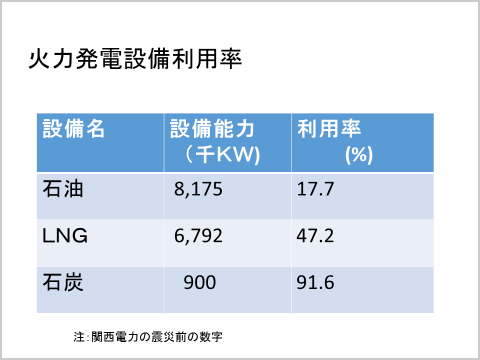
これは火力発電設備の利用率です。電気は貯めるとすごくお金がかかるので、基本的に貯められません。また、一年や一日の中でも電力需要がすごく変動するので、需要が大きいときだけ動く発電設備が必要です。
日本でその役割を担っているのは、燃料代の高い石油火力です。これは関西電力の震災前の数字ですが、石油火力は年間20%も動いていません。九州電力だと石油火力の稼働率は3%ぐらい。つまり、一年のうち10日間しか動かない設備ということになります。そういう設備を持つと大変ですが、誰かが作らないといけないものなんです。
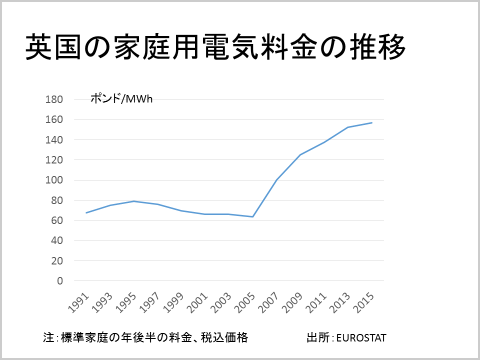
しかし、電力を自由化すると、誰もこういう設備を作らなくなります。イギリスは1990年に自由化しました。年月が経つにつれ、古い発電所は閉まっていきました。誰も設備を作らないので設備が減っています。今年はいろいろな事情があって、イギリスの冬の電力予備率は1.6%。設備が1個止まれば停電というところまで追い込まれました。イギリス政府はいま必死です。電力を自由化した結果、イギリスでは電気代が一時的に下がりましたが、その後にものすごく上がりました。設備が減ってきたら電気代が上がるのは当然です。
 イギリスではこの冬、新電力が倒産しました。卸電力の価格が上がってしまったからです。「安く電気を売ります」と約束したが売れなくなり、その途端に倒産宣言しました。続けるほど赤字が増えるわけですから当然です。ですから、電気を自由化して電気代が下がるというのは、どうも世界の例を見ると非常に難しい。 イギリスではこの冬、新電力が倒産しました。卸電力の価格が上がってしまったからです。「安く電気を売ります」と約束したが売れなくなり、その途端に倒産宣言しました。続けるほど赤字が増えるわけですから当然です。ですから、電気を自由化して電気代が下がるというのは、どうも世界の例を見ると非常に難しい。
ちなみに、いまアメリカで最も信頼されている経済学者はポール・クルーグマンというニューヨーク市立大学の先生ですが、彼は、「市場に任せてはいけないものが3つある」と言っています。一番目は教育、二番目は医療、三番目は電気。電気を市場に任せても安くはならない。逆に電力供給を止めて、値段を上げるような会社が出てくる。電気は必需品ですから、そういうことをすると大問題ですね。電気というのは非常に難しい商品だと思います。
|