|
奈良林 奈良林です。あとで硬い話になると思うので、最初は少し軟らかい話をさせていただきます。
 私の祖母の弟で奈良林祥という大叔父がいます。前にテレビに出ていたことがあるのでご存じの方がいらっしゃるかもしれません。大叔父は性医学者として、夫婦間を幸せにするために自分の一生を捧げた人です。ちょうど大叔父がアメリカで研究活動をしていたころ、日本で「成長の限界」という本が出版され、これから21世紀に入るとエネルギーがなくなるというのを読んだのがきっかけで、私は大学でエネルギーの研究を始めました。それから東芝で27年間、その後いまの大学で5年経っていますから、私もひょっとすると、エネルギーに一生を捧げることになるかもしれません。
私の祖母の弟で奈良林祥という大叔父がいます。前にテレビに出ていたことがあるのでご存じの方がいらっしゃるかもしれません。大叔父は性医学者として、夫婦間を幸せにするために自分の一生を捧げた人です。ちょうど大叔父がアメリカで研究活動をしていたころ、日本で「成長の限界」という本が出版され、これから21世紀に入るとエネルギーがなくなるというのを読んだのがきっかけで、私は大学でエネルギーの研究を始めました。それから東芝で27年間、その後いまの大学で5年経っていますから、私もひょっとすると、エネルギーに一生を捧げることになるかもしれません。
私は、人類にとって大事なのは「愛とエネルギー」だと思っています。人類の幸せのためには愛も必要だし、エネルギーも必要。そこで今日は、エネルギーの話を中心にしたいと思います。

まずこの図をご覧ください。棒グラフは、その年にどれだけ二酸化炭素が排出されたかを示しています。あとで説明しますが、1769年という節目の年があり、その後に産業革命が起きて、大気中の二酸化炭素は第2次世界大戦後に急上昇しています。非常に薄い大気の中にどんどん二酸化炭素が排出されていて、現在はその量が増えています。この夏の猛暑では、日本でも熱中症で倒れた人がたくさんいましたが、こういう異常気象がどんどん増えています。
さて、1769年はワットの蒸気機関が発明された年です。この発明が産業革命につながり、世界は大きく変わりました。それまでは手作業でものが作られていましたが、大きな工場や機械を使って、ものが大量生産されるようになった。それとともに人類が多くのエネルギーを使うようになりました。その後は石炭、石油の時代になり、現在もエネルギー消費量はどんどん増えています。
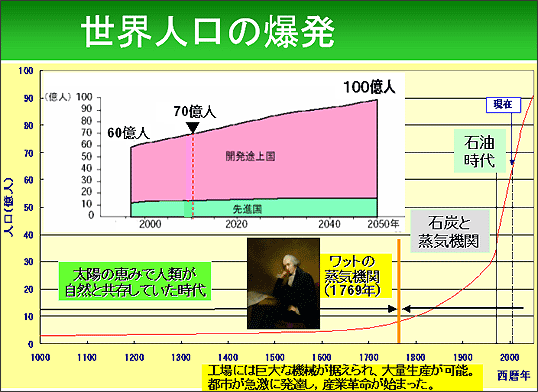
一方、世界人口は今年で70億人を突破しました。2050年には100億人になるだろうといわれています。そんなに遠い未来ではなく、すぐ目の前に100億人を超える時代が迫っています。
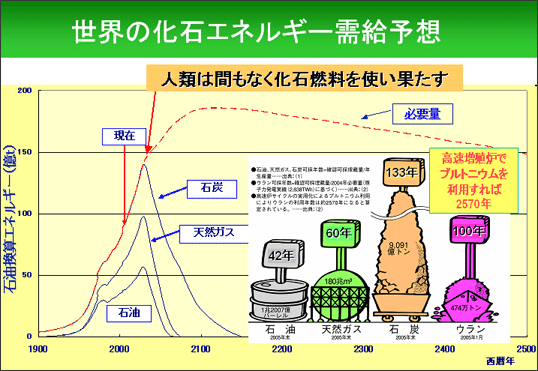
そういう状況でエネルギーがどうかというと、西暦2000年をはさんで石油や天然ガス、石炭を使っています。これらの化石燃料のうち、ある程度長持ちするのは石炭だけ。石油や天然ガスはこれから資源の奪い合いとともに、もっと早くなくなってしまう。
原子力の燃料のウランはあと100年持つといわれています。これから開発しなければならないのは高速増殖炉です。日本では「もんじゅ」に力を入れていますが、高速増殖炉を人類がきちんと使いこなせるようになると、2000〜2500年分のエネルギーをまかなえるようになります。エネルギーの必要量を示す赤い破線がありますが、これと実際に供給できる量とのギャップを埋めることが大事です。ほかに太陽光や風力などもありますが、この中でいちばんしっかりしているのは、私は原子力だと思います。
ただ、世界の状況を見ると、石炭や天然ガス、石油などのエネルギーで人類のほとんどが生きていることになります。原子力や水力などの二酸化炭素を出さないエネルギーはほんのわずかです。ですから、石炭や天然ガス、石油を使って効率良く発電することが非常に大切です。しかし、世界的には非常に大量に消費されており、これらをなるべく使わないで済む発電方法が望まれています。それには水力や原子力などをきちんと使っていくことが重要です。
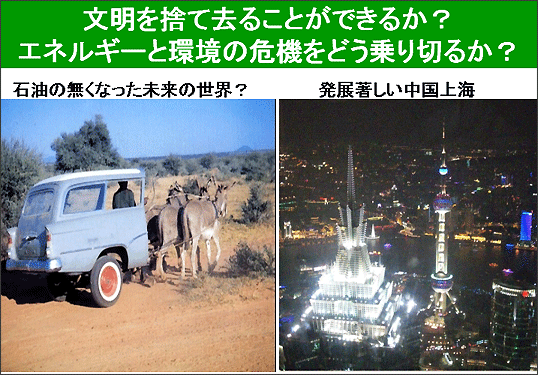
2つの写真のうち、左側は石油がなくなってしまった場合。車はガソリンがないとエンジンが利かない。そのため馬車が車を引っ張っています。このまま何もしないでいると、ひょっとしたらこういう時代になってしまうかもしれません。
右側は中国・上海です。先日、上海で行われた原子力の国際会議に出ましたが、そのときに撮ったのがこの写真です。東京を上回るような高層ビルが林立して、大量にエネルギーを使っています。先ほど宮崎さんのお話にあったように、中国は日本よりもエネルギーを使う国になっています。
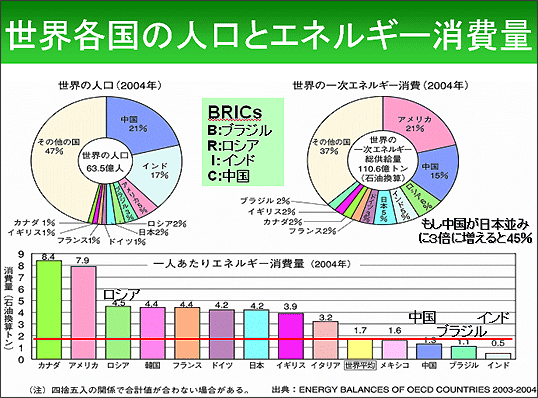
経済発展の著しい国々のことを「BRICs(ブリックス)」といいます。ブラジル、ロシア、インド、中国の英語読みの頭文字を取ると「BRICs」となります。これらの国のエネルギー消費を見ると、世界平均で一人あたりがどれくらいエネルギーを使っているかを示すグラフでは、石油換算で1.7〜1.8トンです。先進国は約4.4トン。アメリカやカナダは非常に多いですね。中国、ブラジル、インドなどは多いですね。特に中国とインドが、先ほどの写真のように上海並みのエネルギーを使うとしたら大変なことです。中国は、いま世界のエネルギー消費量の約15%を占めていますが、国中で使うようになれば約45%になり、世界中の半分くらいを中国が占めるようになってしまう。これにインドが加わると、さらにエネルギーの奪い合いになるでしょう。既に足りなくなっている石油や石炭などの資源がもっと早くなくなってしまう。これをどうにか食い止めなければいけません。
|