|
今年も「新春エネルギー講演会」にお招きいただきまして、ありがとうございます。そして、遅ればせながら、あけましておめでとうございます。そして、もっとおめでたいことは、昨年12月22日、泊発電所3号機の営業運転が開始されたこです。これで北海道の電力も、当分の間は大丈夫でしょう。
昨日、北海道電力の方とお話ししたら、「動き始めた泊3号機で、近いうちにプルサーマルを実施したい」とおっしゃっていました。いまは安全審査をしている段階とのことです。また、泊3号機の営業運転によって、温室効果ガスの排出削減については、目標をほぼ達成できそうだとのことでした。心からお喜びを申し上げたいと思います。
この新春エネルギー講演会では、これまで「原子力を巡る最近の諸情勢」という演題で10年間務めさせていただきました。今日はさらに「泊3号機完成を振り返って」という副題ですので、この3号機が完成するまでの10年間に、世の中がどのように変わっていったかというお話から始めたいと思います。
スライドをご覧ください。「新春エネルギー講演会一覧表」という資料です。
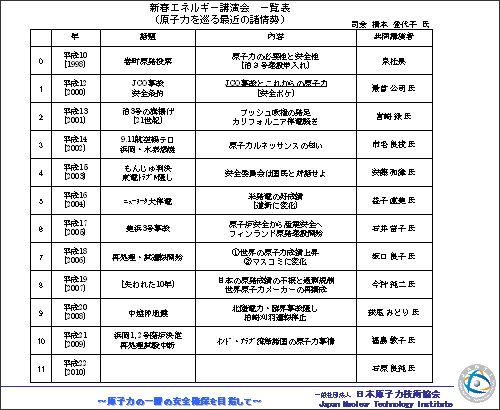
「原子力を巡る最近の諸情勢」という演題でお話をさせていただいた最初が、12年前の1998年10月でした。このときはちょうど、北海道電力が国に対して泊3号機の建設申し入れを行ったときで、当時の泉社長の決意表明に続いて、この演題で講演を致しました。会場はホテルロイトン札幌で1600人が来場され、大入り満員でした。そのときにお話した内容は「原子力の必要性と安全性」でした。まだそのようなことを話さねばならぬ時代だったのですねぇ。また、講演会の主催者団体は、「原子力発電推進道民会議」でしたが、2000年から「北海道エナジートーク21」という名称に変わり、新春講演会が始まりました。
1999年に起こったJCO事故、原子力発電で起こったものではありませんが、日本で初めて死者を出した原子力事故でした。そのため第一回の新春講演会の演題は、「原子力を巡る最近の諸情勢」ではなく、「JCO事故とこれからの原子力」でした。このときに"安全ボケ"という言葉を使いましたら、その後いろいろなところで使われたようです。
それ以降2001年から今年までの10回は、ずっと「原子力を巡る最近の諸情勢」という演題で通しています。その間の講演内容を見てみますと、泊3号機の旗揚げ(2001年)、9.11同時多発テロ(2002年)、高速増殖炉もんじゅの判決(2003年)、東京電力のトラブル隠し(2003年)、ニューヨークの大停電(2004年)、関西電力の美浜発電所3号機事故(2005年)など、前年に起きた原子力問題を取り上げてお話しています。2008年は新潟県中越沖地震の話題でしたが、柏崎刈羽発電所は2007年の地震発生時からつい最近までの約2年間、運転が止まっていました。
ここで注目していただきたいのは、最初の1998〜2000年です。この時期の北電の努力が、泊3号機の今日完成に非常に大きな影響を与えています。
泊3号機の建設申し入れの1998年は、北海道知事が横路さんから堀さんにバトンタッチして4年目のことでした。道内は原子力発電に対して、まだ好意的ではなかった時代です。当時北海道大学にいた私は、北海道電力の泉社長から「泊3号をやろうと思うが、まだ時期が早いだろうか」という相談を受けたことがありました。私は無責任なことが言える立場でしたから、「ぜひおやりになるといい。むしろやらなければいけませんよ」などとお話ししたものです。このときの泉社長の努力が実りましたね。翌年9月半ばまでに地元関係の了解がまとまり実行に移りましたが、それからわずか約2週間後の9月30日に、例のJCO事故が起きたわけです。
2週間遅れていれば、今日の泊3号の完成は、数年は遅れたことでしょう。その意味で、当時の泉社長の決断が非常に大きかったことをお伝えしておきましょう。泊3号機の完成に通算12年もかかっていることに、皆さんは「ずいぶん時間がかかった」と思うかもしれません。でも最近の世界の原子力発電所の建設動向を見ると、これはおそらく、最短記録といえるのではないでしょうか。試運転もつつがなく行われましたし、昨年中に営業運転を開始できたというのは、泊3号機関係者の皆さんが非常に努力をされた結果だと思います。
|

