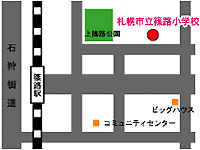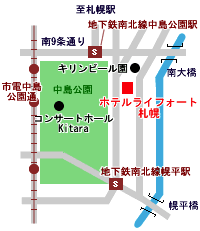|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
平成21年11月13日(金)・14日(土)開催第3回 北海道エネルギー環境教育研究大会
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
本委員会は、多様なエネルギー環境教育の推進を図ることを目的に、エネルギー環境教育に関心を持つ教育関係者の研究・交流の場として8年前に設立されました。 さて、今年度は「持続可能な社会を目指し、自ら行動する力を育むエネルギー環境教育」を新たなサブテーマに、様々な活動を行っており、これまでの成果を全道の皆様に発信すべく、第3回北海道エネルギー環境教育研究大会を開催いたしました。 |
| 主 催 | 北海道エネルギー環境教育研究委員会 | ||||||||||||||
| 後 援 |
北海道教育委員会、札幌市教育委員会、北海道小学校長会、 北海道中学校長会、北海道高等学校長協会、札幌市小学校長会、 札幌市中学校長会、北海道PTA連合会、札幌市PTA協議会、 日本エネルギー環境教育学会、エネルギー環境教育情報センター |
||||||||||||||
| 期 日 | 平成21年11月13日(金)・14日(土) | ||||||||||||||
| 会 場 | 1日目:札幌市立篠路小学校
(札幌市北区篠路4条9丁目3番1号) 2日目:ホテルライフォート札幌 (札幌市中央区南10条西1丁目) |
||||||||||||||
| 参加費 | 無料 | ||||||||||||||
| 日程:1日目(11月13日)札幌市立篠路小学校 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| 日程:2日目(11月14日)ホテルライフォート札幌 | |||||||||||||||
|
|||||||||||||||
| ●公開授業【小学校】 |
| A | 【社会科5年】 授業者:細田 裕也(札幌市立南郷小学校) |
| 単元名「工業生産を支える人々」
便利で私たちの生活に欠かせない自動車の生産に携わる人々が、移り変わる消費者や時代のニーズに応じて、様々な工夫や努力を行っていることを、「今の時代には?」という観点で学習していきます。 |
| B | 【家庭科5年】 授業者:白澤 美江(札幌市立篠路小学校) |
| 単元名「料理って楽しいね!おいしいね!」
5年生になって初めての調理実習、これから2年間の家庭科学習を見据えて、一人一人が調理の基礎基本を身につけるだけでなく、環境に配慮した「エコクッキング」を意識しながら実践できる子どもに育って欲しいと願って授業づくりを行いました。 |
| C | 【理科6年】 授業者:南條 徳一(札幌市立篠路小学校) |
| 単元名「電気の利用」
様々なエネルギーに変換されることで生活に役立てられている電気。その電気を手回し発電機やコンデンサを使うと自分の手で作り出したり蓄えたりできることを学びます。さらに、発電や蓄電のきまりについて調べて、調べたことを生かしながら「自分の手で作った電気を生活に役立てたい」という意識を培っていけるような授業を展開していきます。 |
| ●公開授業【中学校】 |
| D | 【社会科1年】 授業者:東 岳史(北海道教育大学付属札幌中学校) |
| 単元名「北海道のエネルギー」
今回の授業は、「北海道の電力供給の現状」を他県との比較を通して理解し、学んだことがらを自分たちの生活にどのように反映させていきたいかを考える内容としました。中学1年生の段階であるので、現状を認識するという点に重きを置きつつも視点を拡げ、2・3年生におけるエネルギー環境の学習につながっていけばよいと考えています。 |
| E | 【理科1年】 授業者:森山 正樹(札幌市立宮の森中学校) |
| 単元名「いろいろな物質とその性質」〜プラスチックとその性質〜
札幌市では7月から、家庭から出るごみの回収が有料になりました。私たちの身のまわりには、たくさんの物質が溢れており、それらは最後に"ごみ"になります。この単元では、生活と密接にかかわっている"ごみ"の分別方法に視点をあて、科学の目で物質をとらえることをねらいます。とくに、新学習指導要領で新たに履修することになった"プラスチック"は、種類や量がもっとも多いごみのひとつです。公開授業では、プラスチックの性質をMD法によって交流しながら探究します。その後、プラスチックごみのゆくえを考えながら、プラスチックの材料となるエネルギー資源の石油に対しても視点をあて、私たちの生活の在り方を考えます。 |
| F | 【技術・家庭科3年】 授業者:長谷川 寿(札幌市立栄中学校) |
| 単元名「エネルギーの変換と利用」
今回の授業ではエネルギー資源の有効利用と技術の発展という視点を大切にし、簡易火力発電装置と熱電併給装置(コージェネレーションシステム)を活用しながら、発電時に発生する廃熱(無駄な熱エネルギー)をどうにか利用することができないだろうかという内容の授業を行います。そして、これから持続可能な社会を目指すためには、節約・節電といったエコライフの実践や電化製品の省電力技術の進歩・発展といった省エネルギー化だけではなく、石油や天然ガスなどの限りあるエネルギー資源の中から利用可能なエネルギーをできるだけ多く取り出す技術とその活用が大切であることを学びます。 |
| ●記念講演【お天気から見た環境問題】 |
| 講 師 | 菅井 貴子(気象予報士、フリーキャスター) | ||||||||||||||
| 演 題 | 「お天気から見た環境問題」 | ||||||||||||||
|
≪講師経歴≫
|
|||||||||||||||
|
≪講演内容≫
|
|||||||||||||||
| ●会場案内 |
| 【1日目】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
| 【2日目及び1日目のレセプション会場】 | |||||||||||||
|
|||||||||||||
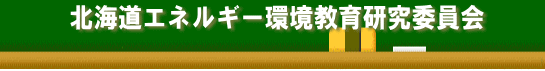
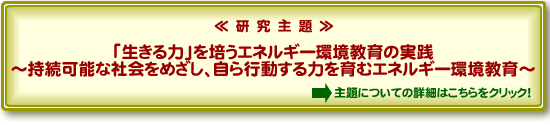
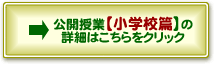
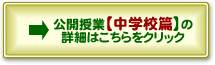

 お天気キャスターとして、最も恐ろしい言葉のひとつが、「観測史上一番」です。たとえば、観測史上一番の大雨とは、観測の歴史100年以上を有する北海道において、少なくとも、100年間は、経験したことのない雨が降った、という意味です。
お天気キャスターとして、最も恐ろしい言葉のひとつが、「観測史上一番」です。たとえば、観測史上一番の大雨とは、観測の歴史100年以上を有する北海道において、少なくとも、100年間は、経験したことのない雨が降った、という意味です。