
 A 「小学校4年生 社会科」
A 「小学校4年生 社会科」
「安全なくらしとまちづくり 雪とくらす」
〜札幌らしさから考えるエネルギー〜
授業者:小森 広幸(札幌市立幌東小学校)
責任者:小林 俊晴(札幌市立真駒内曙小学校)
- 授業の目標
大雪から生活や安全を守るために関係の諸機関が相互に連携して、緊急に対処する体制をとっていることを、地域の人々の生活と関連付けて理解させる。
- 授業の概要
・学習課題 「なぜ雪をためているのだろう?」
・モエレ沼公園「ガラスのピラミッド」の写真の提示 → 課題の把握へ
・既習事項(札幌市の除雪システム)との関連
・自分の考えの整理、発表
・活発な全体交流と公園の方のお話(VTRの活用)をもとに検証

- エネルギー環境教育との関わり(指導上の3つの視点)
・札幌らしい特色ある学校教育「雪」の学習
・「雪」を自然エネルギーとして活用する
・雪冷房システム(現象に触れる) → 「扇風機」と「氷送風機」を使って
・「雪」の可能性と自然エネルギーの大切さ → 思考・判断・表現
- 分科会の話し合いから など
- 成果と課題
◎地域の特性と環境との関わりを関係付けられた。
◎身近な自然エネルギー(雪)の可能性を示唆できた。
◎焦点化した課題により見方、考え方が深まった。
◎興味、関心がわき、問題意識がもてる資料だった。
●自分たちのできることを今後も継続的に考えていく。
●資料の中で扱う数値を吟味することの大切さ。
- 研究仮説との関わり
資料をもとに思考・判断し、実体験を通して追求することができた。

 B 「小学校6年生 理科」
B 「小学校6年生 理科」
「電気の利用」
〜火力発電モデル実験〜
授業者:狩野 量(札幌市立南郷小学校)
責任者:森 剣治(札幌市立川北小学校)
- 授業の目標
手回し発電機などを使い、電気の利用の仕方を調べ、電気の性質や働きについての考えをもつことができるようにする。
- 授業の概要
・学習課題 「火力発電機で発電した電気で光に変換するにはどうすればよいか 。」
・発電にはたくさんのエネルギーが必要であることを理解する。
・火力発電実験機でつくった電気を光に変えられるかどうか調べる実験
・強い火力にして蒸気の威力を増す実験

- エネルギー環境教育との関わり(指導上の3つの視点)
・火力発電のモデル実験の学習、電気のつくり方と使われ方の理解
・人間生活を支えるエネルギーについての概念形成
・日常生活の中でのエネルギー利用に関しての見直し
・自分の手で電気をつくり、蓄え、利用する活動 → 現象に触れる
・エネルギーからエネルギーが生まれることの実感 → かかわりに気づく
- 分科会の話し合いから など
- 成果と課題
◎消費電力に目を向ける
◎生活と結びつけた学習展開
◎電気をエネルギーとしてとらえる
◎他教科とのつながり、発展を生む学習
●火力発電機を取り入れた単元構成と問題解決のあり方
●課題解決に向けての豆電球とLEDの利用の仕方
- 研究仮説との関わり
電気をエネルギーとして実感し、電気の利用の仕方を学ぶ。

 C 「小学校6年生 家庭科」
C 「小学校6年生 家庭科」
「くふうしよう! 季節に合うくらし」
〜身近な住環境を入り口に〜
授業者:鈴木 愛沙(札幌市立幌南小学校)
責任者:濱野 りな(札幌市立南月寒小学校)
- 授業の目標
教室の暖かさや明るさを調べる活動を通して、暖房器具や照明器具に頼る生活を見直し、健康の視点から自然の力を生かした住まい方の大切さを理解させる。
- 授業の概要
・学習課題 エネルギーを利用する他に寒い生活を快適に過ごす方法はないか?
・自然との共生 関連を理解する
・子どもたち自身で確かめる場・時間・教具の保障
・既習(理科の学習)との関連
・振り返りで個々の考えや思いを価値づける
・1日の日射取得熱量相当の灯油3.5L
・活動を振り返りエネルギーに対する見方を高める

- エネルギー環境教育との関わり(指導上の3つの視点)
・温度と湿度を調べる活動を通して、快適な生活を具体的にイメージでき実践できるようにする学習
・自然の力を生かした住まい方の理解
・教室の様々な場所の温度や照度を測定 → 現象に触れる
・子どもたちの学びを見取り、考えを価値つける → 関わりに気づく 判断、表現
- 分科会の話し合いから
- 成果と課題
◎身近な日光を教材化し、温度や照度を数値で表すことにより、日光の力を明確にすることができた。
◎子どもが自分の手で確かめたり結果を交流したりする場、時間、教具を保障することで、友達と考えを照らし合わせながら活動することができた。
●エネルギーを実践化するための具体的な手立て
- 研究仮説との関わり
自然の力を利用した住まい方を焦点化することで新たな生活を作り出そうとする意識が高まった。

 D 「中学校3年生 社会科」
D 「中学校3年生 社会科」
「日本経済の課題」
〜エネルギーと日本経済の関わり〜
授業者:村上 志行(札幌市立上篠路中学校)
責任者:菅谷 昌弘(教育大附属札幌中学校)
- 授業の目標
経済と環境、エネルギーの関連性を理解し、「豊かさ」「豊かな社会」について考え、これからの日本経済の在り方を考えることができる。
- 授業の概要
・学習課題 「限りあるエネルギー資源を大切に使いながら現在も将来も経済的に豊かな社会を形成していくためにはどうすればよいか」を考える。
・持続可能な社会を形成するためにエネルギー問題に関心をもち、主体的に社会に参画しようとする意識を高める。
・自分の考えを書く グラフ、データの読み取り グループ内交流 発表 全体交流
・【ワークシートより】
*今できなくても、これからの技術の進歩でできるようになることもあるので、未来を築く僕たちが一生懸命に考えることが一番の近道だと思います。
*いろんな問題が出ると思うが、その問題を完全に解決するのではなく、いかに解決に近づけるかが大事だと思いました。
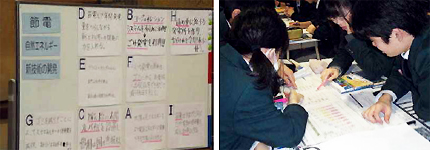
- エネルギー環境教育との関わり(指導上の3つの視点)
・経済発展とエネルギー使用
・これからのエネルギーの在り方
・発電に関するグラフやデータの読み取り → 具体的な事実
・エネルギーに対する考えのグループや学級での交流 → 関わりに気づく
- 分科会の話し合いから
- 成果と課題
◎他教科との横断的な学習
◎自分ごととしてのエネルギーのとらえ
●資料を根拠に多面的に考えるトレーニング
●エネルギーを教材化する視点の明確化
●次の単元とのつながり
- 研究仮説との関わり
社会科として、「指導上の3つの視点」について、「現象に触れる」に関しての研究が今後の課題となる。

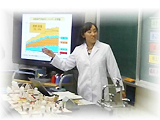 E 「中学校2年生 理科」
E 「中学校2年生 理科」
「身の回りの物質(固体)」
〜プラスチックの油化からエネルギー問題や環境問題を見つめよう〜
授業者:岩本 明子(札幌市立柏丘中学校)
責任者:村上 知嗣(札幌市立啓明中学校)
- 授業の目標
各照明器具の特性について進んで調べることができる。
実験結果やエネルギー資源の枯渇の現状、環境とのかかわりを理解した上で電気の利用を自分なりに考え、表現することができる。
- 授業の概要
・学習課題 「私たちはどのように電気を利用していけばよいか。」
・エネルギー問題、環境問題の確認と整理
・照明器具を入り口に電気の利用を考える。
・環境を意識した電気の利用について考える。意見を交流する。
・モジュール的学習を活用した活発な観察・実験、意見交流
・学習課題の追究に積極的

- エネルギー環境教育との関わり(指導上の3つの視点)
・電気からエネルギー資源の考察、電流の利用の理解
・電球の比較実験 → 現象に触れる
・環境を意識した電気利用を考える → 関わりに気づく 判断、表現
- 分科会の話し合いから
- 成果と課題
◎事前調査を活かした単元構成
◎実感をともなう活動
◎モジュール的学習の活用(多角的な見方)
◎過去の学びを活かした学習
●この学習をうけた3年次の単元構成(系統性の意識)
●エネルギーから環境への切りかえしの発問の工夫
- 研究仮説との関わり
電気利用を環境を意識しながら自己決定できた。

 F 「中学校3年生 技術・家庭科」
F 「中学校3年生 技術・家庭科」
「新しい技術とこれからの生活」
〜ワイヤレス伝送、新しい技術〜
授業者:川崎 勉、名久井 あけ美
{三浦 雅美(理科)、塚崎 亮(社会)}(札幌市立中央中学校)
責任者:児玉 大(札幌市立北辰中学校)
- 授業の目標
日常の生活の中でのエネルギーがどのように利用されているか振り返り、今後のエネルギー活用について考える。
- 授業の概要
・学習課題 「新しい技術を生活に生かすためにはどうしたらよいだろうか 」
・LEDの点灯実験(ワイヤレス伝送)、新しい技術の「評価」
・新しい技術への関心、実用化へのアイディア
・他の教科(理科・社会)との関連
・持続可能な社会の構築へつながる新しい技術の「評価」の重要性

- エネルギー環境教育との関わり(指導上の3つの視点)
・新しい技術の理解 技術を「評価」すること、プロセスの学習
・LEDの点灯実験 → 現象に触れる
・新しい技術の紹介(電動歯ブラシ等) → 関わりに気づく 判断、行動
・技術の「評価」と日常生活との関連 → 関わりに気づく 判断、行動
- 分科会の話し合いから
- 成果と課題
◎事前のアンケートからの課題設定 → 関心・意欲の高まり
◎製品の紹介 → 日常生活との関わり
◎他教科との関連 → 知識の再確認・思考の深まり
◎新しい技術の「評価」の重要性
●エネルギー環境教育との関わりの明確化
●日常の授業への応用(時数の制限)
- 研究仮説との関わり
指導上の3つの視点を、適切に授業に組み込む → 生徒の意識の高まり 表現の変化へ

 G 「中学校1年生 道徳」
G 「中学校1年生 道徳」
「郷土愛4-(8)「山口運河」」
〜郷土愛、地域に根ざした教材〜
授業者:高原 健(札幌市立星置中学校)
責任者:長和 聡(札幌市立八条中学校)
- 授業の目標
地域社会の一員としての自覚を持って郷土を愛し、社会に尽くしている地域の人々に尊厳と感謝の念を深め、自らも郷土の発展につとめる。
- 授業の概要
・身近な太陽光パネルから導入をはかる。太陽光パネルの理解
・山口運河から郷土愛を深め、今後の環境問題を考える。
・清掃活動への感情の変化
・主人公が道徳的に気づいたことを理解する。道徳的実践意欲への高まり
・太陽光パネルの意義の再確認

- エネルギー環境教育との関わり(指導上の3つの視点)
・道徳内容項目4-(8)の学習
・郷土愛への理解
・生徒の生活環境から教材化を狙った → 具体的な事実
・郷土愛と自然愛護に気づく → 関わりに気づく
- 分科会の話し合いから
- 成果と課題
◎身近な教材から、郷土愛・自然愛護の気持ち高まり
◎地域をより深く理解することができた
●道徳は環境から考えさせることができるが、エネルギーとの関わりに課題が残った。
●24項目のうち、郷土愛・自然愛護・愛校心がエネルギー環境教育と関連できる。
●道徳とエネルギー環境教育がつながりあう教材を生み出し、道徳が価値観をつくりあげていく。
- 研究仮説との関わり
カリキュラムの中でお互いに連携していく重要性

 H 「高等学校3年生 理科、地学」
H 「高等学校3年生 理科、地学」
「火山とマグマ、エネルギー」
授業者:松田 義章(道立あすかぜ高校)
責任者:金澤 豪(道立月形高校)
- 授業の目標
火山の活動の実態、マグマの活動と火山活動の多様性、さらに火山の恵みと、エネルギー資源としての活用、災害・防災・減災について興味・関心を持たせ、基礎的事項について理解させる。
- 授業の概要
・学習課題 「火山の噴火はどのようなしくみで起こるのか。火山噴出物と火山の持つエネルギーの活用」
自然との共生 関連を理解する
・火山の噴火を映像で確認する
・火山噴出物の観察、特徴を理解する
・自然エネルギーの活用について理解する
・ワークシートを活用した活発な意見交流

- エネルギー環境教育との関わり(指導上の3つの視点)
・火山についてエネルギー資源と環境の観点からの学習
・火山の持つエネルギーの理解
・火山現象及び火山噴出物の観察 → 現象に触れる
・エネルギー資源として火山の活用 → 関わりに気づく 判断、表現
- 分科会の話し合いから
- 成果と課題
◎火山現象と生活のかかわり
◎火山噴出物から地球内部の状況を理解する
◎ワークシートを記入しマグマのエネルギーの活用を知る
◎自然エネルギーの長所、短所を理解する
●継続的なエネルギー環境教育の展開
●他の単元との関わりの強化
- 研究仮説との関わり
エネルギー資源としての火山の活用を考え、エネルギー問題を自分ごととしてとらえさせる。エネルギー資源の問題解決へと関心を向けさせる。
|